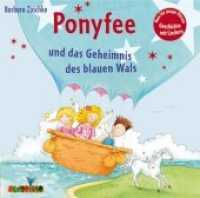出版社内容情報
和服、和装、和食……、私たちになじみ深い「和」の一字だが、これは一体何を意味しているのだろうか。歴史をさかのぼってこの国の生活や文化を一望すると、海を越えてもたらされる文化を受容・選択し、さらに変容させた力が見えてくる。日本の詩歌もまたその創造力によって育まれた。俳句の実作者が和の核心を読み解く快著。
内容説明
日本文化は涼しさの文化である。それは、この蒸し暑い日本列島に暮らす人々が外来文化を、夏を基準にして、作り変えてきたものだからである。異質のものを受容し、選択し、変容させる力を具体的に考察し、創造力に満ちる「和」という運動体の仕組みを解き明かす。それは同時に日本文化についての名随筆、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』が孕んでいた問題に迫る新しい『陰翳礼讃』論でもある。
目次
第1章 和菓子の話
第2章 和の誕生
第3章 なごやかな共存
第4章 取り合わせとは何か
第5章 間の文化
第6章 夏を旨とすべし
第7章 受容、選択、変容
第8章 桜の話
著者等紹介
長谷川櫂[ハセガワカイ]
1954年熊本県生まれ。俳人。俳句結社「古志」前主宰。「きごさい(季語と歳時記の会)」代表。朝日俳壇選者。句集に『虚空』(花神社、読売文学賞受賞)、評論集に『俳句の宇宙』(サントリー学芸賞受賞)などがある。読売新聞に詩歌コラム「四季」を連載、インターネットサイト「俳句的生活」で「ネット投句」「うたたね歌仙」を主宰している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とむ
1
「和」という概念についてあらためて考えさせられる内容。「和」において、「間」や「取り合わせ」がどのように関係しているかも興味深かった。2022/07/27
linbose
0
★★★★★ 俳人長谷川櫂による日本文化論▼和とは、外来文化をまず全面的に受け入れ、次に取捨選択した上で、日本の生活や文化にふさわしい形に作り変える(受容、選択、変容)という創造力である。戦後の日本人はそのような和の創造力を見失い自信を失っているのではないかと。排外思想蔓延の所以か▼和とは、似たもの同士の和気藹々(馴れ合い)ではなく、異質なもの、相容れないものがぶつかり合い、引き立て合いながら共存する状態であるとも。その和を成り立たせるものが、取り合わせであり、間であり、暑苦しい気候条件でもあると2025/09/27
老齢症状進行中
0
十数年ぶりに改訂された本で、前著も読んでいたはずですが、初めてのようにサクサクと一気読みでした。下手な解説はやめますが、著者の言うようにこの「和」の思想が、日本の新たな創造力となってくれることを願うのみです。なんでも取り込んで受容し変容してしまった日本。西洋の科学文明と個人主義もそうできるかな。2024/09/01