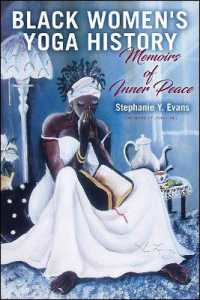出版社内容情報
上方落語研究・評論家としても第一人者であり、多くの著作を残した桂米朝。中でも、上方落語をはじめ広く芸能・文化に関する論考・考証を収めた「上方落語ノート」は代表作として名高い。第一集には「花柳芳兵衛聞き書」「上方芝居噺の特質」「ネタ裏おもて」「考証断片」「寄席のお囃子」などを収録。全四集。解説・山田庄一
内容説明
上方落語研究・評論においても第一人者であり、多くの著作を残した桂米朝。中でも、上方落語をはじめ広く芸能・文化に関する論考・考証を収めた「上方落語ノート」は代表作として知られる。収集した資料を読み解き、芸界の古老への聞き書きなども交えて綴られた貴重な記録。博識の著者の面目躍如である。(全四集)
目次
小栗判官と新町橋
花柳芳兵衛聞き書
上方芝居噺の特質
二代目旭堂南陵聞き書
口合いだんだん
戦後の上方落語家たち
ネタ裏おもて
考証断片
明治の上方新作落語
寄席のお茶子さん
寄席のお囃子
著者等紹介
桂米朝[カツラベイチョウ]
1925‐2015。落語家。重要無形文化財保持者(人間国宝)、文化勲章受章。作家・正岡容に師事し、その勧めで四代目桂米團治に入門、三代目桂米朝を名のる。六代目笑福亭松鶴らとともに、戦後上方落語の復興に尽力した。上方芸能研究・評論でも定評がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gonta19
123
2020/7/22 楽天ブックスより届く。 2022/4/10〜4/12 桂米朝師匠の貴重な上方落語に関する記録全4巻のうちの第1巻。明治以降の上方落語の歴史から、今はあまり高座にかからなくなったネタや、今では通じなくなってしまった「言葉」など、口伝が基本の落語の世界にあって、この記録は本当に貴重である。残りも楽しみだ。2022/04/12
へくとぱすかる
65
以前から読みたいと思っていたので、文庫化に飛びつく。まさに上方落語の貴重な歴史資料。米朝師匠の入門は戦後だが、話は遠慮なく明治・大正、江戸期にまでさかのぼる。落語がいかに歌舞伎など、古典芸能をふまえて作られたか、かつてそれを理解できる客層が存在したかが紹介されていく。落語が一時期衰退したのは、古い文化と軌を一にしているわけで、現在の落語が、私たちにも楽しめる形なのは、生きた芸として変化をともなうからだと理解した。お役所主義へのアイロニー「ぜんざい公社」の原型が明治時代なのは驚き。2020/06/05
fwhd8325
52
落語を芝居と表現する噺家さんがいます。ひとりで何役も演じ分けるのですから、芝居に違いないと思います。そして、その芝居を効果的に演出しているのは上方落語だと思います。鳴り物やはめものと言った効果は、江戸落語にはない大きな魅力だと思います。米朝さんは、上方落語の象徴のような方で、孫弟子にあたる方も米朝一門であることを誇りに感じていることがよくわかります。このシリーズが、岩波文庫から出版され、今のところ第四集まで発行されています。落語だけでなく、文化を語るその内容は大変貴重なものだと思いながら読んでいます。2020/07/18
gtn
30
戦後、幾何もなく亡くなった初代桂小南の実演に触れたことがある著者。目の当たりにしただけではなく、サワリ、語り口、仕草等すべて頭に残している。「たしかに巧い人」「実に間の良い人」と小南を評しているが、著者が書き残さなければ、そんな実感もとうにこの世から消え去っていたことだろう。日常を記録する重要性に気付かされる。空気のように当たり前なものほど、興味の対象にされず、歴史に埋もれる可能性が高い。例えば明石家さんまがそう。幸い、さんまの評伝が最近発刊されたが。2022/01/07
浅香山三郎
17
青蛙房から刊行されていた著作の文庫化。全4冊からなる。落語家としては勿論、落語をはじめとする藝能全般の研究者としても知られた米朝師の論考を収める。明治~戦前期の落語興行のチラシや聞き書きなど、資料集としても興味深い。論考は多岐にわたるが、たとえば、古い落語のなかで使はれるオチの元ネタさがしといふ探究は興味深い。元ネタは、成立当時の芝居の台詞や、ことわざからきているものが多く、米朝師が習つた演者にもオチの意味が不明なものがかなりあつたらしい。この元ネタさがしは江戸明治の庶民文学の研究といつてもよく、↓2021/03/08
-
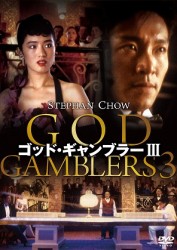
- DVD
- ゴッド・ギャンブラー Ⅲ