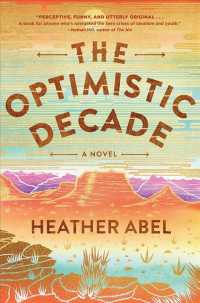出版社内容情報
批評のことばはどこに生きているのか。その生にもつ意味と可能性を、思考の原風景から明らかにする。
内容説明
批評に背を向けても、私たちは生きられる。だが、もし批評がこの世に存在しなかったら、私たちの思考は、いまよりもっと貧しいものになっていただろう。学問とも哲学とも異なる、「自分で考えること」を手放さない批評―その営みが世界と切り結ぶ思考の原風景から、批評が私たちの生にもつ意味と可能性を明らかにする。
目次
1 批評とは何か(この本のタイトル;僕が批評家になったわけ;文芸批評と批評の酵母;原型としての『徒然草』)
2 批評の酵母はどこにもある(対談;注;手紙、日記、きれはし;人生相談;字幕・シナリオ;名刺;科学論文;マンガ)
3 批評の理由(もし批評・評論がこの世になかったら;公衆、世間、一般読者;戦争と批評;無名性)
4 ことばの批評(批評のことばはなぜ重く難しいのか;なぜやさしいことも難しいのか;なぜことばは二つに分かれるのか;電子の言葉の贈り物)
5 批評の未来(平明さの基礎;批評と世間;「面白い」と批評の基準;一階の批評へ)
著者等紹介
加藤典洋[カトウノリヒロ]
1948‐2019年。文芸評論家、早稲田大学名誉教授。著書に、『言語表現法講義』(岩波書店)で第10回新潮学芸賞。『敗戦後論』(ちくま学芸文庫)で第9回伊藤整文学賞、『小説の未来』『テクストから遠く離れて』(朝日新聞社/講談社)の両著で第7回桑原武夫学芸賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件