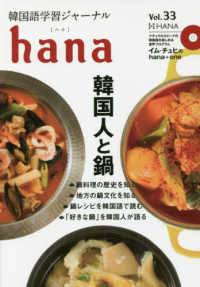内容説明
幼い子どもが一つひとつ言葉を覚え、使うようになる道のり―それは徴笑ましいだけでなく、日本語の不思議や面白さを照らしだしてもくれる。『サラダ記念日』で広く知られる歌人は、シングルマザーとして、いとしい息子の興味深い表現や発想を受けとめながら、言葉のキャッチボールを堪能中。その至福の時間を、柔らかな感性と思考でつづる。あらたに「木馬の時間」三十六篇を増補した。
目次
1 ちいさな言葉(かなしいおべんとう;エサをまく;英語で、だっこ ほか)
2 木馬の時間(木馬の時間;子どもと遊び;プレゼントの季節 ほか)
3 続・木馬の時間(バレンタインデー;曲の名は;朝のできごと ほか)
著者等紹介
俵万智[タワラマチ]
歌人。1962年、大阪府門真市に生まれる。早稲田大学第一文学部卒業後、神奈川県立橋本高校教諭を四年間つとめる。佐佐木幸綱に師事。86年、「八月の朝」で角川短歌賞、87年、第一歌集『サラダ記念日』を出版、翌年同書で現代歌人協会賞、2004年、『愛する源氏物語』で紫式部文学賞、06年、歌集『プーさんの鼻』で若山牧水賞を受賞。「心の花」所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
311
たくみん(俵万智さんのご長男の愛称)の2歳半から、5歳の幼稚園卒園間近までを描く子育て日記。彼の「言葉」に寄り添って、その発達段階と過程を母親として見守り、自身も大いに楽しんだ記録だ。まだ2歳児だった頃のたくみんが「抱っこ」を英語で言うと「どぅわっこ!」じゃない?などと、なかなかの才能を見せる。それを喜ぶ万智さんの親ばかぶりも微笑ましい。後半は、時々短歌付きのエッセイ。「揺れながら前へ進まず子育てはおまえがくれた木馬の時間」。子育てはやっぱりたいへんなのだけど、もう2度と味わえない、それは「木馬の時間」。2016/03/03
ムーミン
41
再読。改めて俵万智という人の言葉のセンス、感受性のすごさを感じました。言われればそうだなと思うことでも、日常の中では簡単に見過ごしている、聞き逃していることばかり。やっぱりすごいなあ。2021/11/28
UK
24
テーマが一見似たような「孕む言葉」と比べるとずいぶんとただの「お母さん」である。言葉に敏感な歌人としてのエッセイを期待するとやや肩透かしを食う。自ら親バカという表現が文中にもあるが、ホントに普通のべったり甘いお母さん目線のエッセイ。けど子供に対する温かみがあって読後感は悪くはない。だた味わいが単調で大量には食べられないかな。もうちょっとさ、せっかくなんだから歌人しようよ。 2016/04/07
ヨクト
24
俵万智さんの息子さんとの言葉を紡ぐ日々。子供が言葉を一つずつ覚えていく道程は輝きに満ちている。ひとつひとつの覚えたての言葉たちが愛おしくて、息子さんが愛おしくて。そのちいさくて、おさない言葉たちは、時に難しい言葉の羅列よりも伝える力を持っている。嗚呼、ぼくもこんな時代があったのだろうか。2013/10/08
サラダボウル
15
俵万智さんの、お子さんが幼稚園の頃の日々のエッセイ。こどもは名詞から言葉を憶えていく(忘れていくのも名詞から?と思わず思う)等、筆者らしい視点がある一方、幼い子との日々を温かく楽しむ様子が伝わる。14才まで大阪で育ったと、時折大阪弁が混じるのも新鮮。この本の執筆中は仙台に住んでいて、仙台の銘菓「くじらもなか」を紹介しており、行ってみたい!食べてみたい!と気になる。私自身の子育ては殆ど終了しているので、「これもいい思い出になる」という男それは未来の私が決める という本書の中では違う光のある短歌が心に残った。2022/02/19