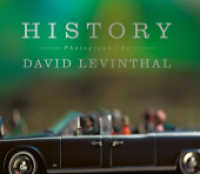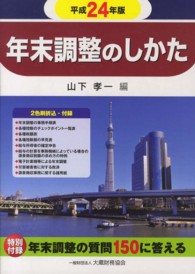内容説明
日本各地の遺跡から出土した石笛や琴、『枕草子』や『源氏物語』、芭蕉の句などに表現された日本の音に作曲家ならではの分析が展開される。さらに民俗芸能・社寺芸能の綿密な調査に基づいて作曲された氏独自の合唱作品『シアター・ピース』が産みだされる過程が克明に述べられる。本書は作曲に向けてのフィールドワークの記録であり、自己解説の書である。
目次
日本の音を聴く(「こをろ」と「もゆら」;縄文の石笛;天の磐笛 ほか)
芭蕉が聴いた音の世界
昔の音、今の音(日本の楽器;オーケストラの音色とその歴史;縄文・弥生の楽器 ほか)
いま、何のために音楽するのか―民俗芸能・社寺芸能による作品の成立について
(『追分節考』;『萬歳流し』;『北越戯譜』 ほか)
著者等紹介
柴田南雄[シバタミナオ]
1916‐96年。作曲家・音楽学者。東京生まれ。1939年東京大学理学部卒業。43年同文学部卒業。東京芸術大学、放送大学などで教鞭をとる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。