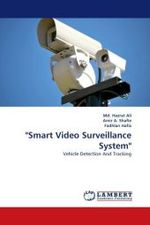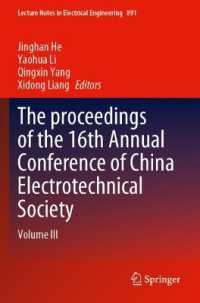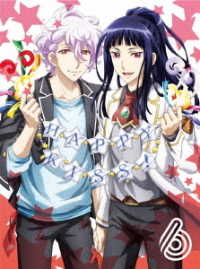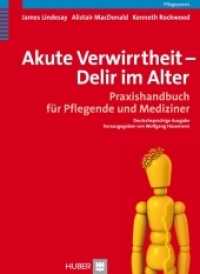内容説明
人びとはどのように教育を受けたのか、そして教育を受けたことがその後の人生にどのような影響を与えたのか―学校、社会、家族…それぞれの眼差しのなかで子どもが教育を受容してゆく過程を、国民国家による統合と、様々な地域・階層の民衆による反発や対抗、捉え返しとの間の複雑な反復関係(教育経験)として捉え直す。現代文庫版では、肢体不自由児、在日朝鮮人や占領地の子どもの教育経験を検証した補章を付す。
目次
第1章 就学と進路をめぐる動向―農村と都市
第2章 国家と学校の望む子ども像―一八九〇~一九三〇年代
第3章 村の子ども像の輪郭―一九二〇~一九三〇年代
第4章 都市の子ども像の輪郭―一九二〇~一九三〇年代
第5章 教育の社会的機能と社会移動
第6章 戦時下の少国民―農村と都市の対比
第7章 学童集団疎開から戦後へ―吉原幸子の戦時と戦後
おわりに―民衆の教育経験とは何だったのか
補章 戦時下の本土と占領地の子どもたち
著者等紹介
大門正克[オオカドマサカツ]
1953年千葉県生まれ。一橋大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。都留文科大学、横浜国立大学等を経て、早稲田大学教育・総合科学学術院特任教授。日本近現代史・社会経済史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
10
疎開者の日記などの一次史料を丁寧に読み込んで書かれた近代日本の教育史。国家や親や地域社会がどのような子供像を描き、子供がそれにどう応えたかが時代の変遷とともに描かれている。普通の歴史書では無視される子供たちであるが、彼らは後に大人となって歴史を動かす主体でもあり、詳しく研究する必要性を感じた。2020/11/12
いあ
0
個人の経験に深く分け入っていきつつ、ときに全体を見渡す作業を経ることで、これまで捨象されてきた歴史の断面を当時の社会に即して見ることができたと思いました。「学校の望む子どもとの落差、異同、ズレ、葛藤、矛盾…(中略)…このような矛盾的過程こそが歴史研究の重要な対象であり、規範や原理の指摘と異なる歴史研究固有の領域だと考えている。」(300頁)という文章が印象的でした。2025/03/07
ふら〜
0
国民統合としての教育、その歴史を農村と都市部の学校記録や生徒の日記を手掛かりに紐解いていく。実際の記録をもとに記載しているため臨場感があり面白い。2021/10/30