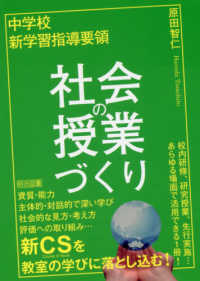出版社内容情報
新旧二つの皇室典範の形成過程を歴史的に検証、日本国憲法下での天皇・皇室のあり方について議論を深めるための論点を提示する。
内容説明
新(戦後)・旧(明治)二つの皇室典範の制定過程で、ともに論議の的となった「天皇の退位」「女帝」「庶出の天皇」の可否という三つの焦点を、憲法学の泰斗が法解釈学的に再吟味し、日本国憲法の下での天皇・皇室のあり方について議論を深めるための論点を提示する。下巻では、明治期に皇室典範が形づくられた過程を、井上毅や伊藤博文ら為政者の構想、民権結社の議論や法制官僚の意見書など、多彩な資料を読み解きつつ検討する。
目次
第2部 明治皇室典範の成立過程―「近代化」と「萬世一系」(皇位継承をめぐって―「庶出ノ天皇」「女帝否認」;「天皇の退位」否認をめぐって;「萬世一系」と「天皇の不自由」との関係)
著者等紹介
奥平康弘[オクダイラヤスヒロ]
1929‐2015年。東京大学名誉教授。憲法学専攻。九条の会呼びかけ人、立憲デモクラシーの会共同代表などを務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おとん707
10
上巻に引き続き天皇の生前退位、女帝、庶子の天皇禁止について憲法との整合性を考察。憲法に皇室典範のこれらの規定を単純に照らせば違憲とも見えるが、一方で皇室そのものが多大な特権とその代償としての制限を持っているのであり皇室の存在自体がそもそも法の下の平等にそぐわないと。結局憲法の持つ内部矛盾が議論を引き起こす根本原因という事らしい。なお終盤に来て筆者の見解が表に出るようになったがそれは憲法学的見解でありイデオロギー的見解ではない。ところで大正天皇を含めその前連続9代に亘って庶子の天皇だったことは知らなかった。2025/08/23
Masatoshi Oyu
6
本書の関心の中心は、日本国憲法の価値体系と天皇制の関係といえるだろう。天皇制は日本国憲法の中にありながら、両者の原理は矛盾している。例えば、前者は平等原則を掲げるが、後者では女帝は認められず、庶系の皇位継承も認められていない。それでだけでなく、職業選択や婚姻の自由など、天皇(皇族)は、その特権と引き換えに様々な人権制約を受けている。 2019/12/03
まさにい
5
学術論文なのだが、読んでいてふと寅さんと天皇が偶然会ったらどんな会話になるのだろうと考えていた。例えば、皇太子時代の留学先で(多分イギリスなのだろうが)、寅さんもイギリスに来ていて、そこで会ったら面白いのではないか。若き日の皇太子が、自分が天皇になるその窮屈さを寅さんに語る。そのとき寅さんは何と言うのだろうか。そんなことを考えていた。女帝論も視点を変えると、皇室の女系は結婚により離脱の自由が確保されていると考えることもできる。天皇からすれば、女系の方が人間的に保障されているとも言えるのかな。2023/07/27
Eiji Nanba
0
下巻では、明治憲法の制定と期を同じくして作られた戦前の「皇室典範」において「万世一系」が如何に組み立てられたかを、一次資料を丹念に読み込んで語っている。この当時から「女帝」「生前退位」「庶出天皇」といった内容が検討されていたことに驚きました。読んだのが夏季休業中でよかったです。内容が濃すぎて、読了までかなりの時間を要しました。2017/09/02