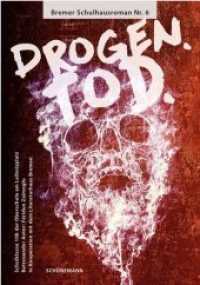内容説明
著者の一大テーマであるスケープゴート(贖罪の山羊)論。中心にある権力は周辺にハタモノを対置して自らの力を正当化し、ハタモノは一時は脚光をあびるがついには排除される。歴史の中で犠牲に供されたトロツキーやメイエルホリドらの軌跡をたどり、スケープゴートを必要としそれを再生産する社会の深層構造をあぶり出す。政治という祝祭空間への独創的接近。
目次
第1部 鎮魂と犠牲(ガルシア・ロルカにおける死と鎮魂;祝祭的世界―ジル・ド・レの武勲詩;日本的バロックの原像―佐々木道誉と織田信長;犠牲の論理―ヒトラー、ユダヤ人)
第2部 革命のアルケオロジー(「ハタモノ」選び;空位期における知性の運命;スターリンの病理的宇宙;トロツキーの記号学;神話的始原児トロツキー;メイエルホリド殺し)
著者等紹介
山口昌男[ヤマグチマサオ]
1931‐2013年。東京大学文学部国史学科卒業後、東京都立大学大学院で文化人類学を専攻。東京外国語大学、静岡県立大学、札幌大学の教授を歴任。「中心と周縁」「スケープゴート」「道化」などの概念を駆使して独自の文化理論を展開した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NICK
9
古代から現代までの社会での政治に通底する構造、「はたもの」の論理。ジル・ド・レーや佐々木導誉のような尋常ならざる過剰性を持つもの、逸脱者は中心的な権力を脅かし、そのことによって脚光を浴びるが、やがて権力によって再び周辺に追いやられる運命にある。彼らは「中心」の再活性化のために贖われる犠牲なのだ。後半のトロツキー論はまさに完全に脱呪術化したはずの共産主義社会すら、こうした祝祭、演劇的宇宙論から逃れられていないことを示している。中心と周辺の再生産(祝祭)が社会の深層であるなら、脱神話化は可能なのだろうか?2015/07/30
柳瀬敬二
6
人は神話によって自らの内面世界に統一的な価値観を形成する。神話には自集団を結束させるための悪、犠牲の祭壇に供される生贄が必要であり、政治的イデオロギーが神話の代替物を務めた時代において生贄とは、ナチス・ドイツにとってはユダヤ人であり、スターリン独裁のソ連にとってはトロツキーやメイエルホリドであった、ということだろうか。レポートの参考文献として目を通したが、ソ連史に関して相当の知識量が読者に求められるあたり時代を感じるというかなんというか…。2015/01/25
坂口衣美(エミ)
5
トロツキーやスターリンといった歴史人物をよく知らなかったので、難しかった…。第一部は面白かった。犠牲を必要とする社会、現代社会にあてはめて考えると、同じことが起こっているのではないかと思える。このようなことは歴史のなかで繰り返されているのだから、今も起こっているのだろう。未来の社会で「当時は○○が犠牲となっていて…」とか言われるようになるんだろうか。2014/07/29
たけぞう
4
ジル・ド・レを扱った論があるので手に取ったが、むしろソ連政治史を祝祭・供犠の観点から読み解く後半の議論がすごく面白かった。2014/08/21
らむだ
3
第一部では権力と“ハタモノ”の関係を中心に据え、第二部ではトロツキーを中心にソヴィエト革命史を辿ったスケープゴート論。歴史・祝祭・神話というテーマを局所的・共時的に語る。2024/09/30