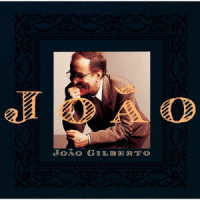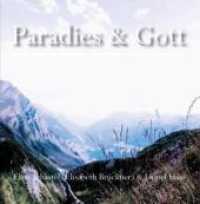内容説明
『茶の本』は、一九〇六年、英文で刊行され、世界に大きな衝撃を与えた岡倉天心の代表作である。日本独自の文化である茶道を通して、東洋の美の根本理念を語る。さらに、東洋の美が、普遍的な霊性に貫かれていることを明らかにした。『茶の本』を、タゴール、ヴィヴェーカーナンダ、内村鑑三、井筒俊彦、山崎弁栄、九鬼周造ら人間の叡知を追究した東西の思想家との接点を探りながら読むことで、新たな天心像を提示する。
目次
第1章 岡倉天心とは誰か(不二一元の世界―ヴィヴェーカーナンダとの邂逅;天心の境涯と生涯;天心の言葉とコトバ)
第2章 『茶の本』を読む(茶道―美の宗教;茶―平和の使者;受肉する茶道;花と永遠;美の使徒・美の使命)
第3章 岡倉天心と東洋の霊性(霊性の宇宙―岡倉天心と山崎弁栄;さまざまなる「東洋」―岡倉天心と井筒俊彦;永遠の詩学―岡倉天心と九鬼周造)
著者等紹介
若松英輔[ワカマツエイスケ]
1968年生まれ。批評家。慶應義塾大学文学部仏文科卒。2007年、「越知保夫とその時代」(『三田文学』)で三田文学新人賞評論部門当選(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
踊る猫
31
「アジアは1つ」と語った岡倉天心について、その思想や生活に実にていねいに寄り添う筆致が魅力的だ。自分自身を超えた存在、つまり神や美なるものや森羅万象といったものとどう向き合うべきなのか。ぼくはついそれらをこの有限にして不十分なぼく自身の尺度に落とし込もうとするが、むしろそうした大いなるものを矮小化する態度を諌め、端的に世界の崇高さに触れることを著者は薦めているのかもしれない。もちろんその態度がはらむ陥穽(危険性)もふまえて。この主張がはらむ構図を、ぼくは粗暴に「スピリチュアル」「神秘主義」と理解したくない2025/02/12
ころこ
25
本書には、「霊」という言葉が頻出します。東洋の哲学、思想、宗教は、西洋のそれらと対照関係にあるのでしょうか。この疑問を常に念頭に置きつつ、読まざるを得ない不自由さは、我々の言葉が西洋の考え方に浸食されたことが原因なのか、そうでないのか。東洋の哲学、思想、宗教がシームレスに繋がっていると感じられる違和感は、全く異なるコンテクストである保田与重郎の「橋」と「茶」が、侘び寂を備えたコミュニケーションツールとして、極めて近いと考える蛮勇を許してくれるのでしょうか。このように、こだわるのは、無造作で思わせぶりな「愛2018/04/22
1.3manen
21
1906年初出(裏表紙)。 愛と天心が書いたのは、存在の根柢にあって万物を生かす働き(3頁)。 窮極的一者の異名。この表現は不思議。 茶道は美の宗教(33頁)。 文化の祖国である中国で失われた茶の霊性は日本の茶道のなかでその命をつないだ(74頁)。 だから、今の領土問題などでは、敵視し合うのではなく、文化の歴史をみるべきであろう。2014/03/06
ひめぴょん
11
岡倉天心の言葉を読み、コトバが顕われるのを待ち生まれた本。鈴木大拙、九鬼周造など関連の深い人とも絡めて。「茶の本」そのものの内容の引用はごく一部ではあるが、天心の精神性を感じる話が多い印象。最終章に書かれていた 父母が亡くなって後の九鬼のエッセイに「(天心に対して)まじり気のない尊敬の念だけを持っている。思い出のすべてが美しい。誰も悪いのではない。すべてが詩のように美しい。」と書かれているのが印象的でした。それに対して著者は「美しさと美しいものは違う。前者は概念だが。後者はいつも実在である。」と書いている2024/03/05
ピンガペンギン
10
岡倉天心に興味が出てきてこの本を手に取った。評伝というよりも、岡倉天心の書(主要なものは全て英語で書かれた)を分析し著者の読みに触れることで著者の思想を知るような部分が多い。ヴィヴェーカーナンダというインドの宗教者(ロマン・ロランによる伝記がある)とは「岡倉とは兄弟だ」と言われたほど似ている部分が多かった。天心の英文は大詩人タゴールが「流れが良い」と賞賛したリズムがあるとのことで、部分的にでも読んでみたい。2022/11/19