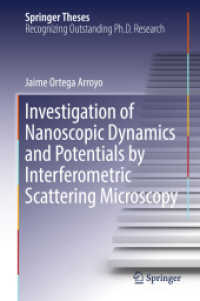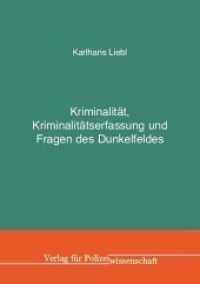内容説明
田中正造の没後百年にあたる今、正造の思想の先駆性と生命力に新たな関心が集まっている。とりわけ「真の文明ハ山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さゞるべし」という言葉に象徴されるその文明観の射程に、三・一一を経て関心が寄せられている。近代日本に根底的な問いをぶつけ格闘し続けた生涯から、私たちは何を学ぶべきか。本書は、正造研究の第一人者が稀有な思想家の全体像を描き、とりわけ正造の思想史的な意義を丁寧に読み解く。
目次
序章 田中正造の人間像―ユーモアの精神を中心に
第1章 田中正造の生の軌跡と足尾銅山鉱毒事件
第2章 「人権尚山河の如し」―人権の思想
第3章 「どこまでもじぶんでやるせいしん」―自立の思想
第4章 自治は「女子の操の如し」―自治の思想
第5章 「真理を中心とする憲法なり」―憲法の思想
第6章 「人民を救ふ学文を見ず」―「谷中学」の思想
第7章 「治水ハ造るものニあらず」―水と自然の思想
第8章 「弱のまゝ」で「弱きを救ふ」―宗教と解放の思想
終章 二一世紀に輝く田中正造
著者等紹介
小松裕[コマツヒロシ]
1954年山形県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。現在、熊本大学文学部教授。日本近代思想史。田中正造と足尾銅山鉱毒事件の研究に三〇年以上取り組み、正造の思想を軸に日本近代思想の可能性を追求している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
35
足尾銅山鉱毒事件と田中正造(1841-1913)◉1-2章_ 71年間の生涯を神格化せずに「敬して遠ざけない」ユーモア精神の持ち主と位置づける導入部。議員として市民として活躍するも、一貫した自己認識は、いち百姓。曰く「夫れ天下の生産は誰の手ニ生ずるや。皆此弱者の手に成らざるハなし」◉鉱毒問題追求の論理を ”公益と所有権“ そして ”生存権を中心とする人権思想“ へと深化させたとまとめる著者。ここで公益については、”当然のこととして差し出す納税感“ と補足されていて、この部分は注意深く読みたい。→2023/03/14
metaller
4
少し前、話題になった田中正造という人はどういう人なんだろうか?とふと手に取った本。 言うまでもなく足尾銅山鉱毒事件で被害地となった谷中村に住み、 経営主である古河(現、古河機械金属株式会社)や時の政府と、住民とともに闘った人。 天皇への直訴でも有名。だが、天皇直訴のみが注目されていて、彼の思想は現在は語られるのは少ないのではないだろうか。この本は「直訴」にはほとんど重きをおいておらず、彼の思想を体系立てて紹介している。 彼の思想・言葉は3.11以降の日本においても十分示唆に富んでいる。 2014/02/17
瓜月(武部伸一)
3
「真の文明ハ山を荒らさず、川を荒らさず、村を破らず、人を殺さゞるべし」 100年前の田中正造翁の呟きが胸にせまる。それは勿論、私が福島原発の無残な光景を目の前にしているからだ。 著者小松氏は、田中正造が足尾鉱毒問題と格闘しながら到達した思想について、「人権尚山河の如し」から「弱のまゝ弱きを救ふ」まで、いくつもの印象的なキーワードで整理をしながら案内をしてくれる。 田中正造没後100年。その間、破滅的な戦争があり、経済復興があり、今がある。谷中村、水俣、そしてまた福島の現実。田中正造の思想は生きている。2014/08/17
れいな
3
『日本人は何を考えてきたか』というNHKの番組を見損ねて、かわりに同タイトルの本を読んだのだが、「明治編」の田中正造に大変興味をひかれてこの本を手にした。とても面白かった。田中正造の「行動する思想家」たるゆえんがとてもよくわかった。それも知識人の政治参加のような軽い意味ではなく、本当に身を以て、「其人民の苦痛二学んで」人を救うことを求めた人なのだということが、よくわかった。2014/02/20
kawara26
2
郡馬出張を機会に購入。学生時代の牧師的イメージとはかけ離れ、一思想家としての人生観に触れられたことはよかったです。そして、それ以上に、足尾銅山事件は今なお、終結していないという現実には衝撃を受けました。3・11以来「原発」しか語られていませんが、それ以外でもまだ終結していない鉱毒問題。我々の、日本の課題は、決して小さくないと思いました。安易な解決ではなく、源流解決を目指したいと思いました。2014/06/19
-

- 和書
- イデア 月と太陽の物語