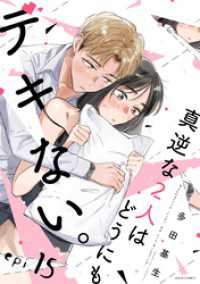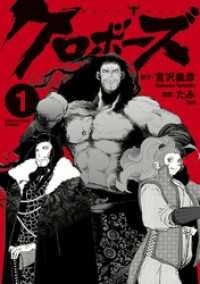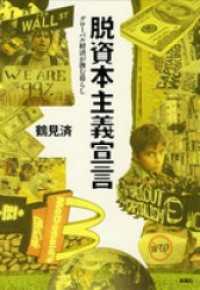出版社内容情報
なぜ我々は疑いもせず取引ができるのだろう.なぜ結婚するのだろう.なぜ宗教を信じるのだろう.なぜ権力が生まれるのだろう.当たり前のこと,合理的なこととして片づけられている日常の生活をめぐる「常識」にひそむ深層構造を,儀礼と象徴の理論を通して脱常識化し解明してゆく社会学入門の定番.新たに1章が書き足された原書第二版.
内容説明
なぜ我々は疑いもせず取引ができるのだろう。なぜ結婚するのだろう。なぜ宗教を信じるのだろう。なぜ権力が生まれるのだろう。当たり前のこと、合理的なこととして片づけられている日常の生活をめぐる「常識」にひそむ深層構造を、儀礼と象徴の理論を通して脱常識化し解明してゆく社会学入門の定番。新たに一章が書き足され、全体に改訂がほどこされた原書第二版。
目次
1 合理性の非合理的基礎
2 神の社会学
3 権力の逆説
4 犯罪の常態性
5 愛と所有
6 社会学は人工知能をつくれるか?
著者等紹介
コリンズ,ランドル[コリンズ,ランドル] [Collins,Randall]
1941年生まれの米国の社会学者。ペンシルベニア大学教授。理論・学説研究を中心に幅広い領域で活躍する
井上俊[イノウエシュン]
1938年生まれ。社会学専攻。大阪大学名誉教授
磯部卓三[イソベタクゾウ]
1938年生まれ。社会学専攻。大阪市立大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NICK
16
エミール・デュルケームの宗教儀礼理論を中心に、合理的にデザインされていると思われている社会が、実は「儀礼」という全く非-近代的、非合理的なものを根本にしているという驚くべき説を提示する、スリリングな社会学入門。我々は「個人」が「主体」的に「自由」に行為することが自明な価値観のように思いがちだが、実はそれすらも根源的には宗教的な「儀礼」があり、その反復がその価値観を支えているというのだ。つまり、こう言ってよければ無根拠性が深奥にある。そうだとすれば「より良い社会」というのはどこまで可能なのか、疑問が浮かぶ2014/10/10
ドラマチックガス
13
学生時代にゼミで初版を読んだ。20年以上ぶりに2版を読んでみた。懐かしい思い出が蘇る。『ランドル・コリンズが語る社会学の歴史』もそうだけれど、コリンズの入門書はわかりやすい。それでいて「交叉いとこ婚」なんて専門用語が注釈もなく出てきてかつてはゼミ仲間と用語を調べながら読みすすめていった。自分で調べた知識は今も残っている。社会学という未知の学問にワクワクしながら読んでいったんだったなぁとシミジミ。あの頃の仲間とこの本でまたゼミをやったら面白いかも。素敵な同窓会になりそうだし、十分に今また読む価値がある。2024/08/17
日輪
10
社会学を学ぼうと思ったら、小難しい思想書よりこれ一冊読めばいいのではと思う。人間はしばしば合理的だと考えられるけど、本当に皆が私利私欲で動いたら、誰も信用し合わず、社会は崩壊してしまう。それでも社会が存在するのは、何らかの儀礼によって社会の象徴(信念?)が共有されるからだとし、非合理的概念の重要性を説明する。その後も儀礼論を援用して、権力の所在の曖昧さ、犯罪の社会的原因、愛と所有の関係を考察する。最後の人工知能の章は、どちらかと言えば「人間らしさとは何か」を述べた内容だと思うけど、会話の参考にはなった。2015/10/07
awe
9
めちゃくちゃ面白い。社会学の面白さを久々に実感。合理的に行動していると思っている我々を支えるのは非合理的な儀礼であるというデュルケム的な話を基調に、権力、犯罪、性愛、家族、人工知能といったテーマを論じ、我々の常識を相対化し、現在の社会のあり方が、いつ、なぜそうなったのかということを記述するスリリングな書き振り。個人的には、後述する彼の「権力」観はかなり新鮮で興奮した。同じ専門職でもなぜ自動車修理工と医者では後者の方が権力があるのか、という素朴な疑問に1つのヒントを与えてくれるような考え方だった。まず1章2022/03/20
Narr
8
一言で述べるなら、合理的で常識とされるものの多くの根本が、それ自体不合理性を孕むものであるということを丁寧に解説してくれる社会学の入門書です。犯罪は無い方が良しとされるものの、実は社会システムには既に犯罪そのものが織り込み済みであり、逸脱者を罰することで逸脱者以外で形成された社会集団の連帯を強化することができる作用があるなど。デュルケムからの引用が多め。