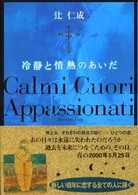出版社内容情報
入矢義高は,唐宋代の口語・俗語を多用した禅語録を,精確に解読することで,文学としての中国禅の理解を画期的に深めた.入矢の「禅と文学」に関する論文,随想を精選してまとめる.求道者は,言語を絶した体験を文学として表現することで,そこに無上の悦びが生まれることが語られる.今回,新たに六篇の論文・随想を増補した.
内容説明
禅語録の語学的・文学的研究を確立した著者による代表的な論文、随想をまとめる。唐宋代の口語・俗語を多用した禅語録を、精確に解読することで、旧来の伝統的解釈に囚われない新たな禅思想の理解が可能にされる。語録、禅僧の詩偈を解読した論文の他に、寒山、董/蘿石、水滸伝、老子など中国古典文学も取り上げて、広く「禅と文学」の問題が論じられる。白居易、明代の文人、敦煌説話等の中国古典文学に関する論文六篇を、新たに増補した。
目次
禅と文学
寒山について
寒山―その人と詩
〓(ほう)居士―その人と禅
董蘿石―その人と詩
中国の禅と詩
禅問答というもの
雨垂れの音
臨済録雑感
禅語つれづれ〔ほか〕
著者等紹介
入矢義高[イリヤヨシタカ]
1910‐98年。中国語学・中国文学専攻。鹿児島県生まれ。京都帝国大学文学部支那文学科卒。東方文化研究所(後の京大人文科学研究所)研究員を経て、名古屋大学、京都大学、花園大学教授を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bittersweet symphony
3
入矢義高(1910-1998)さんの短めの文章を60年代後半から70年代にかけてを中心にまとめたもの。前半は中国禅と詩とのかかわりを語源学的な切り口を中心に語るもの。日本に渡ってきて希釈化される前のきわめて人間くさい禅の様相が窺えます。後半は元・明代の(つまりは漢詩のメインストリームからちと外れている題材の)詩曲について、やはり語源学観点から当時の既成の翻訳テキストのミスリードを正していく文章が中心。2012/11/27
しずかな午後
1
入谷氏は、禅の語録の時代に即した読解を行ったことで知られている。本書は氏の雑文集。禅宗の伝統的な訓読に苦言を呈する「臨済録雑感」「禅語つれづれ」。明末の個性的な知識人たちに思慕を寄せる「ある隠者の死」「水滸伝の序」「酒への惑溺」。“透明な禅者”の評伝である「龐居士ーーその人と禅」。禅学の教理に踏み込んだ「生と死」「空と浄」。どれも勉強になった。禅の語録の研究はまだ始まったばかりであるようなので、今後の研究動向にも注目したい。2020/07/14
-

- 洋書
- Falling-4