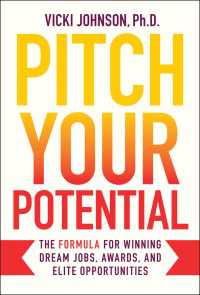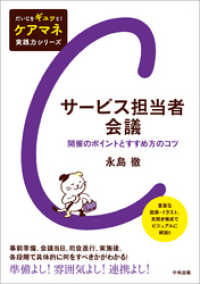出版社内容情報
“戦後”がまだ戦後であった1950年代末、戦争によって混迷に陥った日本人の思想の建直しをめざして行われた白熱の討論。六つのテーマに即して同時代の知識人と大衆の思想を縦横に論じ、その可能性を模索した。
内容説明
“戦後”がまだ戦後であった一九五〇年代末、戦争によって混迷に陥った日本人の思想の建直しをめざして行われた白熱の討論。「近代文学」「民主主義科学者協会」「心」それぞれのグループの思想、生活綴り方・サークル運動、社会科学者の思想、戦争体験の意味、の六つのテーマに即して同時代の思想を縦横に論じ、その可能性を模索した。
目次
知識人の発想地点―『近代文学』グループ
反体制の思想運動―民主主義科学者協会
日本の保守主義―『心』グループ
大衆の思想―生活綴り方・サークル運動
社会科学者の思想―大塚久雄・清水幾太郎・丸山真男
戦争体験の思想的意味―知識人と大衆
著者等紹介
久野収[クノオサム]
1910‐1999年。京都大学哲学科卒
鶴見俊輔[ツルミシュンスケ]
1922年生まれ。ハーバード大学哲学科卒
藤田省三[フジタショウゾウ]
1927‐2003年。東京大学法学部卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
24
ごっつい教養を誇る3人が戦後十数年間の日本の6つの思潮を語り合う誌上シンポジウム。当時の主流の課題を鋭く指摘し、一方で陰に隠れがちな一般人の達成を意義づけていくのだが、今読んでみると後者のほうが圧倒的に面白い。問題そのものよりその状況をつかむ生活綴り方運動にせよ(これは自分の関心の中心でだったが)、個別から離れない戦争体験の読み解きにせよ、「ポジティブな読み」の力強さが光るのだ。その時点では、強者たちへの批判のほうが強く見えたかもしれない。でも、時間の網をくぐることができるのは「肯定」だと改めて実感した。2014/02/03
さえきかずひこ
11
1958年に『中央公論』に連載された報告と討論をまとめたもの。文藝誌『近代文学』、民主主義科学者協会、文藝誌『心』、生活綴り方運動・サークル運動、わが国の社会科学者の思想ーとりわけ大塚久雄(経済史)、丸山眞男(思想史)ー、戦争体験のもつ意味の差異と多様性(インテリと庶民を比べて、また戦中派と戦後派を較べて)という6つのテーマについて、当時の雑誌『思想の科学』同人であった3人が、滾るような熱情と該博な知識をもって論じ合う。内容は難解な部分もあるが"反体制知識人"たちの気骨のある議論にグイグイ読まされた一冊。2019/11/14
スズツキ
3
かなり難解だが楽しめた。特に戦争文学から当時の大衆思想を読み解いていくところで、取り上げる文学をあらすじを絡めて適時その思考の解題に努めるところは実に良かった。とにかくもっと勉強しないといけないと思いましたわい。2014/04/06
takizawa
2
1959年以来何度も刊行されている本。6つのテーマについて,1人の報告+3人の討論から成る。思想=知識人の専有物という考えではなく,大衆思想(朝日新聞ひととき欄の創設につながるような生活綴り方運動)や戦争体験を語ることの意味についても議論されている。後者は当事者語りに対する批判的考察として現代でも頷けるところがある。二項対立ではなく三分肢で考える立場としての保守主義,アカデミズムと社会運動の関係など,今出されている思想系の本に書いてあることの多くが書いてあるな,という印象。民科のところは歴史の勉強にw2010/10/22
RINA
0
読了。2012/03/22