内容説明
河合隼雄の処女作であり、日本で最初に著されたユング心理学の本格的入門書。河合心理学の出発点がわかる本であり、後に展開する重要なテーマが数多く含まれている。著者の生涯を通じて重要な位置を占め続けたユング心理学に関する最も基本的な本。文庫化に際し、著者がユング心理学を学ぶに至った経緯を自ら綴った「序説ユング心理学に学ぶ」を併録し、「読書案内」を付した。
目次
序説 ユング心理学に学ぶ
第1章 タイプ
第2章 コンプレックス
第3章 個人的無意識と普遍的無意識
第4章 心像と象徴
第5章 夢分析
第6章 アニマ・アニムス
第7章 自己
著者等紹介
河合隼雄[カワイハヤオ]
1928年兵庫県生まれ。京都大学理学部卒業。1962年よりユング研究所に留学、ユング派分析家の資格取得。京都大学教授、国際日本文化研究センター所長、文化庁長官を歴任。2007年7月逝去
河合俊雄[カワイトシオ]
1957年奈良県生まれ。京都大学教育学研究科博士課程修了。ユング派分析家資格取得。京都大学こころの未来研究センター教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
molysk
67
フロイトが提唱した無意識の概念は、その衝動性ゆえに意識の支配下に置かれるべきとするものであった。ユングは、意識と無意識は相補的であり、心を全体として高めるものとする。また、意識を構成する自我とペルソナ、無意識を構成する個人的無意識と集合的無意識、人間の類型における外向と内向、思考と感情、感覚と直観など、対の概念を定義したうえで、全体として統合を深めることが重要である、とするユングの主張は、二元論につながるものであり、東洋思想との親和性が高いと思われる。筆者の河合隼雄は、日本におけるユング心理学の第一人者。2022/10/17
Vakira
55
僕の中には2つの意志が存在する。僕でだけでなく人間は2の意志を持っているようだ。一つは自分を意識として存在している物:自我。もう一つは無意識の意志。本能的な物。例えば心臓の動き。息は意志で止められるが、心臓は意志では止められない。僕に夢を見せるのも無意識の意志だ。ユングさん、自我をペルソナ、無意識をアニマ(こころ)と命名した。ペルソナとは一般には仮面の事で虚実の自分と解釈してしまうが、ここでは外に表現される自我、自分を意識して自分としている物をペルソナとしている。著者河合隼男さん素晴らしい解説。2021/05/08
南北
49
人間の心を読み解いていこうとする本である。心を意識と無意識に分け、さらに意識を自我とペルソナ、無意識を個人的無意識と集合的無意識に分けることで解明していこうとする。内容は決して簡単とは言えないが、著者はできる限りわかりやすく解説しようとしているので、丁寧に読んでいけば納得できることが多い。先日成立したLGBT法案で心は男性とか女性とかの話が出ていたが、そんな単純なものではないことがよくわかる。余談だが、江戸川乱歩の『心理試験』もユングの心理学がベースになっていることを知ることができたのも収穫だった。2023/06/16
ビイーン
31
ユング心理学を大衆向けに噛み砕き分かりやすく書かれている。私は心理学の初心者だが、本書によってユング理論の概要を知ることができた。手元に置いて時々読み返したい本にしよう。第7章「自己」で私自身の現況に当てはまる言葉に出合い少し感動する。ユング理論と東洋思想との比較についての議論なども読んでみたら面白いかもしれない。巻末の読書案内を参考にユング心理学をさらに知りたいと思う。2019/12/27
加納恭史
25
先に読んだジル・ボルト・テイラー著左脳と右脳分析の「ホール ブレイン」でユングの四つの個性がキャラクター1~キャラクター4に対応するとあったので、ユングの入門書で確認してみる。第1章タイプでは次の様。まあ最初のタイプは内向と外向の見方がある。続いて四つのタイプの心理機能がある。ユングはそれを、思考、感情、感覚、直感に分けて説明してゆく。思考と感情は対立関係にある。また感覚と直感もまた対立関係にある。思考の発達している人は感情が未発達であり、感情の発達している人は思考は未発達である。感覚と直感の関係も同様。2024/03/11
-
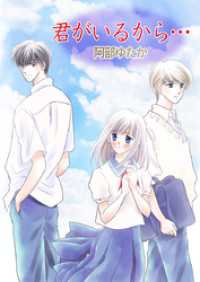
- 電子書籍
- 君がいるから…【タテヨミ】第51話 p…
-
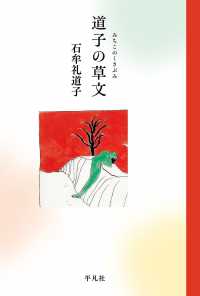
- 電子書籍
- 道子の草文







