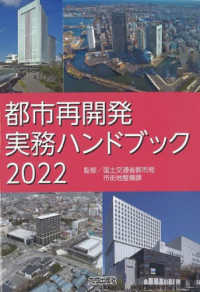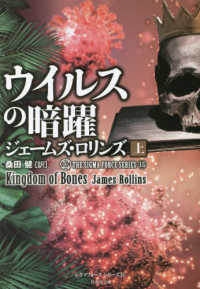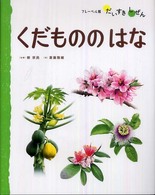内容説明
歌舞伎の美と力、その魅力を解明した碩学による名著。現代演劇との比較を通して歌舞伎の本質をとらえ、古代・中世の芸能など前史にもふれながら阿国歌舞伎から江戸の全盛期を経て近代に至るまでの歴史を叙述。劇場の構造、観客と批評、役柄、作劇術、セリフ、音楽と舞踊、衣裳・かつら・化粧、舞台・道具・照明などについて解説し、歌舞伎の社会性を論ずる。
目次
第1章 かぶきの生き方
第2章 かぶきの本質
第3章 かぶきの歴史
第4章 かぶき劇場
第5章 かぶきの見物
第6章 かぶき役者
第7章 かぶきのドラマツルギー
第8章 俳優術と演出
第9章 かぶきと社会性
著者等紹介
郡司正勝[グンジマサカツ]
1913‐98年。演劇学者。札幌市生まれ。早稲田大学国文科卒業。60‐84年早稲田大学教授。戦後の歌舞伎研究をリードし、日本文化全般の研究にも及んだ。また歌舞伎、日本舞踊、舞踏などの舞台の創造にも精力的にかかわった(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はるたろうQQ
1
かぶきは古典劇であり、民族の無形文化財としての伝承こそが進むべき道だとする。著者のような人々が歌舞伎の社会的地位を上げ歌舞伎役者が文化勲章を受けるようになったが、歌舞伎が本来持つ饗宴性や大衆性を犠牲にした感がある。現代の役者達は文化勲章よりも観客の熱狂を欲していると思う。猿之助のワンピースや菊之助のナウシカ、玉三郎の泉鏡花ものなど、歌舞伎の可能性を拡げ有意義なものと思うが、著者が存命ならば安易な現代化=低俗化として批判されると思う。歌舞伎の歴史的変遷を知るには便利だが、今歌舞伎を観るための入門書ではない。2024/07/30
のの
0
入門とはしつつ、少しは歌舞伎とか歌舞伎じゃないにしろ歴史やらがわからないと辛いかと。最後のエピソード、帝大の水泳部の学生が合宿先で地元の方に歌舞伎をして、それを浜尾総長が怒ったというのが興味深い。学生が歌舞伎を演じられ、地元の人も歌舞伎が分かり、総長が学生の演劇に口を出し、更にシェークスピアならともかく歌舞伎だからダメだという。今では考えられないなぁ。2014/10/07
Yamanaka Shinya
0
かぶきの歴史、思想、その他かぶきを見る際には知っておいたほうがいいことを、お手軽に知ることのできる本。2013/02/26
にゃんこ
0
入門にしては内容が難しい。独特の言い回しに、気合いを入れて読むことを勧めます。2013/01/09
叔嗣(しゅくし)
0
かぶきを残すために学会の人が入門書として手がけた本。考え方が固すぎる。古典の歌舞伎とは何かどうあればいいかはあっても、「かぶく」という事が何なのか一言もなかった。2012/11/03
-

- 和書
- ヘルプ・ミー・シスター