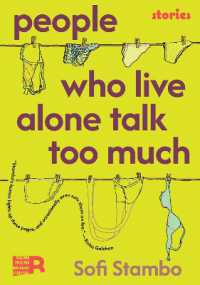出版社内容情報
なぜ歴史的に考える力が必要なのか。それは過去の上に立って、今を生きていることを私たちが忘れがちだからだ。結果、現代で起こる問題を近視眼的にしか捉えられず、社会を息苦しいものにさせている。近現代日本の歩みを振り返りながら、現在進行形の諸問題との連関を検証し、よりよい今、そして未来をつくる意義を提起する。
内容説明
歴史的に考える力が、なぜ、いま必要なのでしょうか。それは過去と対話しながら、ていねいに生きることが、より良い今日、そして未来をつくることにつながっていくからです。近現代日本の歩みをたどりながら、現在進行形の諸問題との連関を検証し、広い視野で物事をとらえていった先に、歴史を学ぶ意義と意味が見えてきます。
目次
序章
第一章 戦争と暴力が繰り返された時代―日清戦争からアジア太平洋戦争の敗戦まで
第二章 占領政策で変わったこと、変わらなかったこと―一九四五~一九五〇年代前半
第三章 苦しみを強いられ続ける人びと―一九五〇年代後半~一九八〇年代
第四章 冷戦終結と終わらない戦争―一九九〇年代~現在
第五章 歴史的な視点から現在の世界を読み解く
終章 「現在」は、過去、そして未来につながる
著者等紹介
宇田川幸大[ウダガワコウタ]
1985年、横浜市出身。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。日本現代史専攻。現在、中央大学商学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
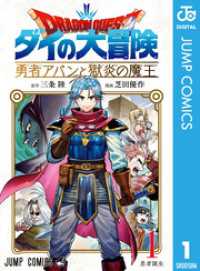
- 電子書籍
- ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者ア…