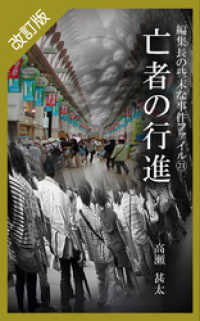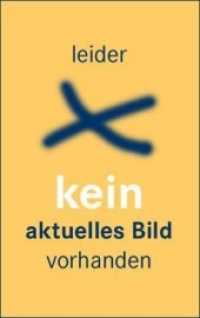内容説明
古代ギリシャからローマ帝国、十字軍、大航海時代、ルネサンス、フランス革命、二つの世界大戦、東欧民主化…、そして現在のEUへと至るヨーロッパ形成の過程をたどります。ユーロ危機をはじめ、様々な困難を克服しながら統合への努力を続ける欧州の歴史と今を描きます。
目次
第1章 ヨーロッパの起点―カエサルから神聖ローマ帝国まで(ヨーロッパの起源;ギリシャとローマ ほか)
第2章 戦争に明け暮れた近代―国民国家と帝国主義、革命の時代(主役が入れ替わる近代ヨーロッパ;スペインとハプスブルク家 ほか)
第3章 不戦の誓いと統合のスタート―独仏連携築いた指導者たち(米ソ冷戦下のヨーロッパ;東西ドイツ分断とNATO創設 ほか)
第4章 一九八九年の革命―ドイツ統一とミッテラン外交(チェコスロバキアの革命;ミッテラン、コールの登場と市場統合 ほか)
第5章 ユーロは生き残れるか―欧州の未来展望(ユーロ発行、「深化・拡大」へ条約改定;デンマークの否決、国民意識とのかい離 ほか)
著者等紹介
明石和康[アカシカズヤス]
1952年生まれ。76年、東京大学文学部西洋史学科卒業。同年、時事通信社入社、外信部配属。サンパウロ特派員、パリ特派員、ワシントン支局長、外信部長、広島支社長、国際室長、解説委員長を経て、現在、解説委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんやん
27
ザックリした内容だな、と表紙を見返すと、タイトルもザックリしてるし、使われている写真もそう。著者は時事通信社の記者を経て解説委員の方。1952年の欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)の発足が統合への第一歩。58年に経済共同体(EEC)と原子力共同体(ユートラム)が発足。英国はこれらに加わらず、北欧諸国やスイスなどと59年にEFTAを結成。しかし、結局、EECやECへ加盟申請するも、拒否される。ド・ゴールに言わせれば、アメリカが送り込んだ「トロイの木馬」だと。戦中戦後どれほどお世話になったのか、忘れたのか。2020/10/17
鮭
10
今のEUはアンリ四世の財務総監であるシュリーに構想に端を発することを恥ずかしながら、初めて知った。大戦争後に何かしらの統合あるいは連帯に向けた機構を考えるのは古来からの欧州の思考なのだろう。EUもまた一日にして成らずといったところである。とはいえ本著のキモは戦後史の部分である。独仏枢軸とはよく例えた表現で、近世以降欧州の大戦争は大体この辺りで生じてきたことを勘案すると、この枢軸により、統合の歩みが急速化するのは自明ともいえる。しかし、EU自体がドイツの独り勝ちになりつつあるのは歴史の皮肉なのかもしれない。2015/02/12
sankichineko
9
元時事通信社の特派員というだけあり、一般人に限られた文字数で的確な情報を与える能力が見事です。20世紀以降の内容が半分以上を占めますが、ヨーロッパの起源から現在までを綺麗にまとめています。かなりざっくり情報を削っているのですが、おかげで歴史の流れが非常に分かりやすい。詳しすぎる本ではかえって要点がわからなくて、「で、結局何が原因だったんだろう・・」と思っていた所が初めて理解できました。(どこかは恥ずかしいので秘密)同シリーズでアメリカのものもあったので、是非読みたいです。2019/06/05
みどるん
5
ほぼ普通の世界史と変わらない内容が、歴史を語る上でのヨーロッパの重要性を示している。ECSCの頃からEUまでの流れをみると、ドイツだけでなくフランスにも勢いが必要だ。2014/07/10
Sumiyuki
4
@(マーストリヒト条約の合意がされた会議直後)ドロール委員長が「我々はサッカーをやろうとしているのに、イギリスはラグビーを持ち込んでくる」と語ると、議長国オランダのファンデンブルック外相は「いやクリケットですな」と苦笑いしながら、記者会見の席上で社会労働政策の強化に最後まで抵抗したイギリスのメージャー首相の態度を皮肉交じりに語りました。2025/06/08