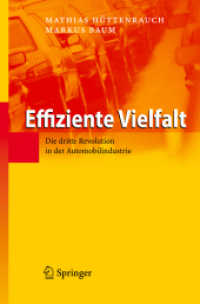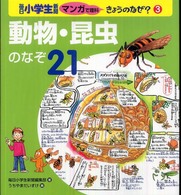内容説明
メンデルが遺伝の法則を発見して100年後、ついに遺伝暗号のナゾが解かれました。その過程は、若い科学者たちが工夫をこらした実験と斬新なアイディアを積み重ねた、わくわくするドラマでした。デルブリュック、ワトソン、クリック、ニレンバーグらが考えたあとをたどりながら、遺伝子のはたらくメカニズムが頭に入ってきます。
目次
1 遺伝子が見つかった
2 本体はDNA?
3 遺伝情報の流れをさぐる
4 遺伝情報の伝わるしくみにせまる
5 暗号解読にいどむ
6 ゲノムの時代へ
著者等紹介
岡田吉美[オカダヨシミ]
1929年静岡市生まれ。大阪大学大学院理学研究科修了。九州大学、大阪大学、オレゴン大学、農林省植物ウイルス研究所をへて、東京大学教授、帝京大学教授を歴任。東京大学名誉教授、日本ウイルス学会名誉会員、理学博士。1996年日本農業研究所賞、2003年日本学士院賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
inami
25
◉読書 ★3 本書は分子生物学の誕生と発展の歴史のなかから「遺伝子の発見から遺伝子暗号の解読まで」にスポットを当て、どの時代にだれが、いつ、どのようなアイディアで、どのような実験をしたのかということが書かれている。本書の発行が2007年3月、遺伝子組みかえが成功し、それを利用したバイオテクノロジーという新しい産業が生まれ・・という段階、それから約15年が経った今、この世界のテクノロジーはどこまで発展しているのだろうか?たぶん想像を絶するような世界になっているのだろう・・へえ〜なるほどと思った部分①、②→2021/07/13
本命@ふまにたす
3
分子生物学の発展の歴史を主にその黎明期を中心にたどる。分子生物学というとかなり難解なイメージがあるが、ジュニア新書らしくわかりやすく書かれているのは好印象。2022/02/01
つる
2
とっても面白かった!特に生物と無生物のあいだを読んだ直後で重複する内容もあったのですが、それぞれの著者の捉え方の違いが分かって面白かったです。ワトソンクリックフランクリンの二重螺旋構造の話とか。5章の遺伝暗号の部分は結構難しかったのでもう一回他の本を読んだ後に読み直したいです。それぞれの発見やその具体的な実験、証明方法がわかりやすく載っていたので疑問に思ったところは頭の片隅に置いておいて今後の勉強に役立てたいです。2014/05/18
Makoto
2
大学の生物学の参考書として買わされた新書。遺伝子の発見から遺伝暗号の解読までの約100年の経緯が記されている。ただ研究の経緯だけが記されているのではなく、その研究をしてきた人達のドラマも書かれていて教科書にはない面白さがある。「若い」研究者たちが生物学の歴史を築き上げていったことが書かれていて、著者が次の若い世代に期待していることが伝わってくる。高校生向けの新書だけど生物やってないと難しいかも。2013/11/27
ティファニー
1
遺伝の解明に迫った科学者たちのドラマを楽しみながら、遺伝の基礎的な内容が学べる。学習した内容でも忘れていることが多くて良い復習になった。2015/03/04
-

- 和書
- 『タイム』でみがく英語