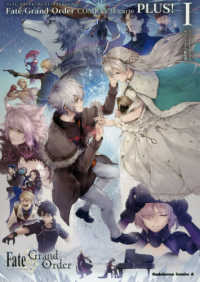出版社内容情報
「大江戸八百八町」と謳われた江戸の町は,同時代のパリやロンドンをも凌ぐ,世界最大の都市だった.この繁栄はなぜ可能だったのか.なぜ260年も泰平の世が続いたのか.その秘密を解明しつつ,徳川15代の御代の魅力にせまる.
内容説明
家康によって幕藩体制が築かれて以来二六〇年、「大江戸八百八町」と謳われた江戸の町はパリ、ロンドンをも凌ぐ繁栄を誇り、また全国に名君が輩出して、わが国は世界的にも珍しい長期の平和を実現した。このような「泰平の世」は一体なぜ可能となったのか?その秘密を解明しつつ、徳川十五代の御代の魅力にせまる。
目次
第1章 江戸幕府の成立と新しい国際関係(戦国時代の終焉;征夷大将軍と江戸幕府 ほか)
第2章 幕藩体制の社会と文化(百姓の増加と村町の交流;武断から文治へ ほか)
第3章 十八世紀の改革政治と社会(公儀政治の改革;田沼の政治と寛政の改革 ほか)
第4章 江戸時代後半の文化(近世人の生活と文化;民間社会の文芸と芸能 ほか)
第5章 内憂外患の時代と復興意欲(世界の変化と海防;町や村で ほか)
著者等紹介
深谷克己[フカヤカツミ]
1939年三重県生まれ。早稲田大学第一文学部史学科国史専修卒業。同大大学院文学研究科史学(日本史)専攻博士課程修了。現在、早稲田大学文学部教授。専門は日本近世史
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
32
参考文献。政治用語など既知のものとして扱っている言葉が多いので、日本史辞典があれば心強い。2015/05/15
coolflat
17
17頁。島原天草一揆には、この当時の社会の矛盾が凝縮されていた。島原半島・天草諸島の農漁民・船稼人・商工町民、関ケ原陣や有馬家の日向転封で生み出された牢人たちは、天草四郎の名で記憶される少年を結集核にして戦った。その背景には、九州をおおった旱魃と飢饉、大名の功名心と畏怖心を掻き立てる江戸城増改築、将軍上洛、東照宮造営ほか種々の助役が転嫁された百姓負担の重さ、取立ての理不尽さがあった。2022/09/04
白義
12
戦国の終わりから幕藩体制整備による秩序の構築という武士の文治への変化と、その平和の中でも社会矛盾に立ち上がった民衆の活動、上と下の両方から江戸時代の全体像を明瞭に書いている秀逸な入門書。260年の平和な社会の中で多彩な民衆文化や思想、哲学が花開き洗練を重ねていった活気あふれる時代を描いている。200ページほどなのに文化や政治、経済まで手堅くまとめている範囲の広さと簡潔さがいい感じ。戦国と江戸、江戸と近代の連続性を伺えるように書いているところも視野を広くさせてくれる点。近世社会を立体的に感じさせる良書である2015/09/29
うえ
6
「村町も請負を制度化した支配になった。武士が村人を剣槍で脅して年貢を取りあげる必要はなかった。村に宛てて一通の割付状が送られ、村高に課された年貢総量を、名主(庄屋・肝煎)が、大小の百姓の所持高に応じて高下なく割付けて徴収し上納する村請制が完成した。村請は戦国時代から徐々に広まり、近世に入ると村と領主の基本関係になった」「『公事方御定書』は、公儀が初めて編纂した判例集で、「御定書百箇条」とも呼ばれた…裁判の促進、追放刑の制限、残酷刑の緩和、縁坐や拷問の制限、時効の制定など、司法にも文治化が進んだ」2017/05/07
nom
2
戦国時代の終焉から、外国が開国を求めてくるまで。2015/08/02
-
![すぐヌけるマリアちゃん[ばら売り] 第34~36話 ヤングアニマルコミックス](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0908863.jpg)
- 電子書籍
- すぐヌけるマリアちゃん[ばら売り] 第…