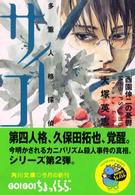出版社内容情報
東京芸術大学の前身、東京美術学校の波乱の歴史をたどりながら、明治維新以後の日本美術の、西洋との出会いと葛藤を描く。フェノロサ、岡倉天心、黒田清輝、横山大観……。国粋と国際派の勢力争いの中、戦争へと突き進む時代にもまれながら、日本美術はいかに模索され、戦後の近代美術へ展開していったのだろうか。
内容説明
東京芸術大学の前身、東京美術学校の波乱の歴史を『東京芸術大学百年史』を手掛かりに、鮮やかに描き出す。岡倉天心、フェノロサ、黒田清輝、そして横山大観…彼らは西洋とどのように向き合い、日本美術を模索したのか。それは国粋と国際派の勢力争いの中、戦争へと突き進む時代の、日本美術の葛藤の歴史でもあった。
目次
第一章 日本はいつ西洋と出会ったか―キーワードは遠近法
第二章 ジャポニスムの誕生―慶応三年パリ万国博覧会への参加
第三章 欧化を急げ―明治初期の国際主義的文化政策
第四章 反動としての国粋主義の台頭
第五章 美術学校設立の内定とフェノロサ、岡倉の欧米視察旅行
第六章 国粋的美術学校の理念の確立にむけて
第七章 開校された美術学校―フェノロサ、岡倉の教育プログラム
第八章 図案科、西洋画科の開設と岡倉の失脚
第九章 一九〇〇年パリ万国博覧会への参加
第一〇章 正木直彦校長時代の三〇年と七ヶ月
第一一章 和田英作校長時代の四年間
第一二章 戦時下の東京美術学校とその終焉
著者等紹介
新関公子[ニイゼキキミコ]
1940年新潟県長岡市生まれ。1965年東京芸術大学大学院修士課程修了、東京芸術大学芸術資料館(現東京芸術大学大学美術館)に勤務(‐1974年)。2002年東京芸術大学美術館教授、現在、名誉教授。専攻、美術史。2012年『ゴッホ 契約の兄弟―フィンセントとテオ・ファン・ゴッホ』(ブリュッケ、2011)で吉田秀和賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひと
ジュンジュン
Cinita
NorthVillageHRE
インテリ金ちゃん
-

- 電子書籍
- 韓国TVドラマガイド vol.107 …