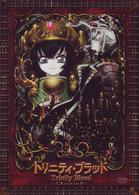出版社内容情報
東アジアで『論語』とならび親しまれてきた『孝経』は、儒教の長い歩みを映し出す鏡のような存在だ。古代における経典の誕生と体系化、解釈学の興亡と皇帝によるテキスト編纂、失われた書物をめぐる日中の学問交流、そして「孝」の教えをめぐるせめぎ合い――小さな古典から、儒教の大いなる流れをスリリングに案内する。
内容説明
東アジアで『論語』とならび親しまれてきた『孝経』は、儒教の長い歩みを映しだす鏡のような存在だ。古代における経典の誕生と体系化、解釈学の興亡と皇帝によるテキスト編纂、失われた書物をめぐる日中の学問交流、そして「孝」の教えをめぐるせめぎ合い―小さな古典から、儒教の大いなる流れをスリリングに案内する。
目次
序章 『孝経』が映しだす儒教の歴史
第一章 書物の誕生と鄭玄による体系化―漢代まで
第二章 『古文孝経』と孔安国伝の謎―魏晋南北朝時代
第三章 テキストが確定される―唐、玄宗御注の成立
第四章 使われる経典に―宋から明清へ
第五章 『孝経』を読んでみよう
著者等紹介
橋本秀美[ハシモトヒデミ]
1966年、福島県生まれ。東京大学文学部中国哲学専攻卒、北京大学古典文献専攻博士。東京大学東洋文化研究所助教授、北京大学歴史学系教授、青山学院大学教授を経て、現在―二松学舎大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
19
新書にありがちなサブタイトルとメインタイトルを逆にすべき例。『孝経』を中心にして見る儒学学術史であり、儒学経典史といった趣。最後の章で鄭注に沿った経文全文の翻訳があるほかは『孝経』の内容そのものはあまり問題にしていないが面白い。今文・古文の対立の図式は清末の政治・学術状況を漢代に投影したものであるとか、鄭玄と王粛の学術上の位置づけの話、特に王粛の議論が意外と穏当であり、だからこそ漢代以来の礼制を受け継ぐ南朝で受け入れられたとか、孔伝が実は『管子』を多く利用しているといった指摘が刺激的。 2025/01/21
電羊齋
16
本書の内容をまとめると『孝経』を軸にした儒教二千年の歴史といったところか。基本を抑えつつ、興味深い指摘も多い。なかでも、今文・古文の対立といわれるものは実は清末民国の政治・学術状況が漢代に投影されたものであるという指摘が面白い。そのほかにも、古今の『孝経』についての議論、唐の玄宗御注、元々為政者の姿勢を示す物であった『孝経』が宋から明清時代に民衆教化のために使われた歴史、明清代での『孝経』の位置づけ、日本での『孝経』の受容と刊本など話題が豊富。巻末には鄭注を元とした『孝経』の翻訳が掲載されており有用。2025/02/09
夜桜銀次
4
第4章までは、中国の歴史の中で、孝経が各々の注釈者によって、どのように解釈されてきたかを追う。門外漢のため追いきれなかったが、今文鄭注と古文孔伝と玄宗注だけ押さえておこうかな。 もともと、支配層が実践する「考」が、民衆も実践すべきとされていくあたりが分かったのも収穫だった。 また、孔伝は『管子』の内容が多いということに驚いた。 第5章で本文(今文)と鄭注に沿った著者訳がある。 同著者による『書物誕生「論語」』があるので、これも読みたくなった。2025/03/20
えふのらん
3
儒教の、科挙の裏の裏、孝経を軸にした註釈者の二千年もの殴り合いを堪能できる本。後漢の鄭玄、魏の王粛、唐の玄宗、南宋の朱子らが先行する註釈に異を唱え、時に修正し、時に新たに付けてしまう様が複雑な関係性と共に描かれている。途中で鄭註に疑問をもった劉知幾が真偽問題に発展させる場面などは今と変わらない文献学のあるべき姿を示しているようで面白かった。儒教というと孝悌忠恕の印象が強いが、そういった上から下への力の流れとは別に文献解釈の精度をめぐる緊張感が常にあったというのは意外だ。2025/04/23
錢知溫 qiánzhīwēn
3
經書…先秦期に成立した文獻は衆多の人々によって累層的に成立したものであり、そこに一個人の統一した意思思考を認めることはできないこと、輯佚書と古書の引用、それらをどう取り扱うべきか、また寫本時代における經典受容の狀況、書物流傳の物質的條件を勘案することなど中國古典を取り扱うで基礎的な認識が提示されている。 《孝經》が成立したと思われる戰國期から《春秋》とともに孔子の精神の精隨を備えた至高の經典と尊ばれた東漢に至るまで、書物の流傳・識字層は限られており、《孝經》はあくまでも統治者のための敎養であった。2025/03/13
-
![H[エイチ] 特別版](../images/goods/ar/web/vimgdata/4988135/4988135559258.jpg)
- DVD
- H[エイチ] 特別版
-

- CD
- 黒岩安紀子/知覧の母