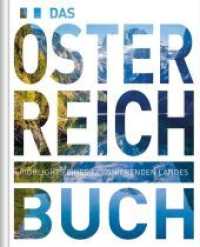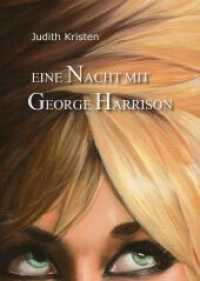出版社内容情報
試験前の一夜漬け。苦労して覚えても、終わればすぐに忘れてしまう。もっと効果的で効率的な学習方法はないのか。鍵は「記憶」にある。記憶のしくみを深く知り、上手に活かせば答えはひらめく。記憶のアウトソーシングが加速するAI時代。人間の創造性が問われる今こそ必要な、科学的エビデンスにもとづく記憶法のヒントを伝授する。
内容説明
試験前の一夜漬け。苦労して覚えても、終わればすぐに忘れてしまう。もっと効果的で効率的な勉強法はないのか。鍵は記憶だ。記憶のしくみを深く知り、上手に活かせば答えはひらめく。記憶のアウトソーシングが加速するAI時代。人間の創造性が問われる今こそ必要な、科学的エビデンスにもとづく記憶法のヒントを伝授する。
目次
第1章 意味づけの効用(人間は意味を求めてしまう;意味と記憶の関係;知識がなければ理解はできない;記憶を確実にする)
第2章 注意の落とし穴(見えているのに気づかない;ワーキングメモリ;マルチタスクの功罪;不安の棚卸し)
第3章 イメージ記憶術(イメージを活用する;百聞は一見にしかず;イメージへの変換;知識を構造化する)
第4章 記憶に根づかせる(効果的な復習方法;アウトプット学習法;スムーズさのわな)
第5章 連想の力(無意識の記憶;記憶の引き出し方;ひらめきは無意識の底から)
著者等紹介
高橋雅延[タカハシマサノブ]
1958年新潟県生まれ。1981年京都教育大学卒業、1986年京都大学大学院博士課程単位取得退学、1996年京都大学博士(教育学)取得。京都大学助手、京都橘大学助教授などを経て、聖心女子大学教授。2023年退職。聖心女子大学名誉教授。専攻、認知心理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ねこ
ねこ
けんとまん1007
TS10
templecity
-

- 電子書籍
- 僕だけがいない街【タテスク】 Chap…
-
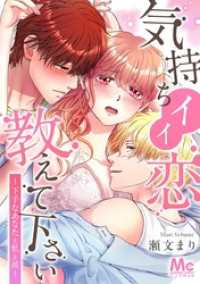
- 電子書籍
- 気持ちイイ恋 教えて下さい~下手なあな…