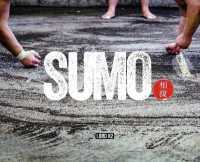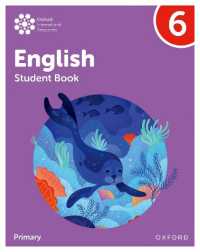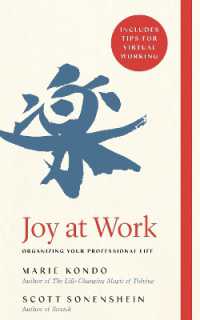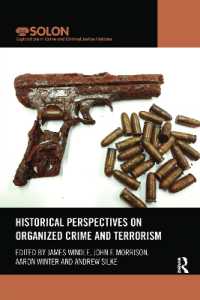出版社内容情報
古代の中国から伝わった漢字は、日本語の内部に深く入りこんだ。はなしことばを視覚化することを超え、漢字は日本語そのものに影響を与えつづけてきた。『万葉集』から近代まで、漢字に光をあてて歴史をたどろう。漢字がつくるさまざまなかたちを楽しみながら、文字化の選択肢が複数ある、魅力的なことばを再発見する。
内容説明
古代の中国から伝わった漢字は、日本語の内部に深く入りこんだ。日本語を視覚化することを超え、漢字はことばそのものに影響を与えつづけてきたのだ。『万葉集』の時代から近代まで、漢字に光をあてて歴史をたどろう。漢字がつくるさまざまなかたちを楽しみながら、文字化の選択肢が複数ある、魅力的なことばを再発見する。
目次
序章 正書法がないことばの歴史
第1章 すべては『万葉集』にあり
第2章 動きつづける「かきことば」―『平家物語』をよむ
第3章 日本語再発見―ルネサンスとしての江戸時代
第4章 辞書から漢字をとらえなおす
終章 日本語と漢字―歴史をよみなおす
著者等紹介
今野真二[コンノシンジ]
1958年神奈川県生まれ。1986年早稲田大学大学院博士課程後期退学、高知大学助教授を経て、清泉女子大学教授。専攻―日本語学。著書―『仮名表記論攷』(清文堂出版、第30回金田一京助博士記念賞受賞)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
64
【正書法がない言語である日本語において、漢字がはたしている「役割」は多岐にわたり、かつ深い】日本語を視覚化するとともに、言葉に影響を与え続けた漢字。「万葉集」の時代から近代まで、漢字の歴史をたどり、文字化の選択肢が複数あることの魅力を説く書。<日本語の文字化に際してはつねに選択肢がある。選択肢があるのだから、文字化のしかたが一つではない。だから「正書法」はない、ということになる。正書法がないというと、正書法のある言語が優れていて、ない言語はだめな言語と思いそうになるが、そういうことではまったくない>と。⇒2024/12/06
bapaksejahtera
20
正書法のない言語という副題につられて読む。無言語時代の後に圧倒的に先進の漢字という表記法を手にした日本は、漢字の語義の咀嚼を優先する。試行錯誤の末、万葉仮名が成立し、更にカナが登場。言語間の形態的懸隔と、語彙概念上の相違が、多様な訓を漢字や漢語に与える。副題はこの謂である。本書は日本語における漢字を巡る取っ組み合いの歴史を述べるが中々難解。時に論旨の散漫も感じるがこれは読み手の学力の不足による。近世の白話小説の流入の画期的な事を諒解する。外国由来と感じない迄の漢字の圧倒的影響は現代に至り寧ろ強まっている。2025/07/12
さとうしん
15
漢字・漢語の読みからたどる日本語(彙)論。話は古代→中世→近世と時代順に進んでいくが、各章で議論されるポイントはそれぞれ異なる。個別のテキストの中での字形などの細かな差異に着目した議論が目立ち、「生のテキスト」を丁寧に読むことの大切さを教えてくれる。万葉の頃には日本語を書き表す文字として漢字をどう使うかという試みは一通り終わっていたのではないかという議論や、かな書きの連綿活字の話、近代中国語の取り込みの話などを面白く読んだ。2024/04/27
chisarunn
6
生まれたときから(生まれてちょっと経ってから)いままで、日本語を使い続けている。ので、英語などと違って日本語には「話し言葉」に対応する「書き言葉」が複数ある、というのは漠然とではあるが誰でも知っている。たとえば英語なら森はForstだけだが、日本語は森・もり・モリ、さらに"杜"でも意味が通じる。著者の言う「正書法」とは正しい書き方が一個だけある、と言う意味で、その点日本語は少なくとも三つあるのが普通なので、正書法がないという表現になっているらしい。ね、面白いでしょ!自分ら、こんな面白い言語を使ってるんだ。2025/07/26
ヘビメタおやじ
6
日本語の複雑さを改めて思いました。万葉仮名は苦肉の策ではなく、それまでの文字化の成果という見方に、はっとさせられました。文字を三種類も持っている、それも他国からもらった表意文字を発展させた言語が文字から影響を受けない筈がないでしょう。今でも、我々は漢語を和語に、和語を漢語に、すり合わせ・置き換えながら生活している実感があります。それは、日本語の歴史を受け継いで生きているということなのでしょう。それは、言語の膨らみ・豊かさとも捉えられますが、あやふやさを生んだともいえるかもしれません。メタ視点、大事です。2024/10/12
-
- 洋書
- Sumo