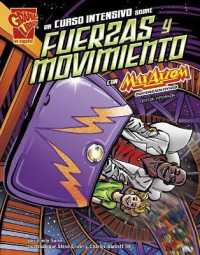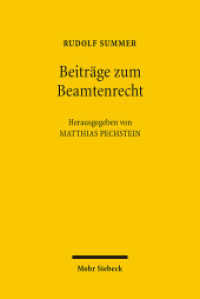出版社内容情報
ビジネス会議ではなぜ雑談が大事? 会話での相づちにはどんな意味が? 大勢での話し合いをまとめる秘訣は?ーー日常の会話やビジネス会議、リスクコミュニケーションといった話し合いを、社会言語学の観点から具体的に分析してみると、「人に優しい話し方・聞き方」がどんなものか見えてくる!
内容説明
ビジネス会議ではなぜ雑談が大事?会話での相槌にはどんな意味が?日常の会話やビジネス会議、オンラインの話し合いやリスクコミュニケーションを、社会言語学の視点から分析してみると、コミュニケーションを成り立たせる条件がみえてくる。誰も排除しない社会に向けた「人に優しい話し方・聞き方」のヒントがここに。
目次
1章 優しさの手がかり―カギとなる概念や理論
2章 雑談のススメ
3章 大切なのは「聞くこと」
4章 難しいコミュニケーション
5章 コミュニケーションデザイン―記述から提案へ
終章 優しいコミュニケーションを考える
著者等紹介
村田和代[ムラタカズヨ]
奈良県橿原市生まれ。ニュージーランド国立ヴィクトリア大学大学院言語学科Ph.D.(言語学)。現在、龍谷大学政策学部教授・学部長。専門は社会言語学(コミュニケーション研究)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hiace9000
103
社会言語学から見た「コミュニケーション論」とはー。著者・村田和代さんの新聞インタビューに惹かれて購入。コミュニケーションが「話し手」「聞き手」の双方で行われる点は既にデフォルト。話し手の語りを受け止める聞き手の姿勢は優しいコミュニケ―ションのツボであり、それ次第で思いや考えの再構築が促され、語り手の自己肯定感につながるというファシリテーターのコツにも気づけた。聴衆を掴む巧いスピーチにみられる、よくやるアレのことを「スピーチアコモデーション」というのか!と。これは新たな学びとしてストックさせてもらった。2025/04/28
けんとまん1007
63
これまでに関心を持って、少しづつ気を配ってきたことが整理できた。コミュニケーションの基本は、双方向であること、話すこともあるが、何より聞くこと・聴くことの大切さにあると思っている。最近読んだ鈴木敏夫さんの本にも「ひとは話そうと思うと聞かなくなる」という主旨のことがあって、その通りと思ったのと響きあう。また、ファシリテーターのことは以前より頭にあって、少しはできているかな。優しい、思いやりの基本にあるのは相手をリスペクトできるかどうかかなと思う。2025/05/24
ジョンノレン
55
前半は比較言語学的?に日本と海外を対比しつつコミュニケーションの諸相に分入っていく。英語では「話し手責任」が重く誤解が生じないよう言葉を尽くすことが求められるのに対し日本語では「聞き手責任」に重きが置かれ話し手の意図を察することが求められ聞き上手が好まれる。円滑な司会で活発で有効な話し合いを導くアドバイスみたいな事がつらつらかと思えば、コロナ禍の際の東京や大阪の知事や首相のスピーチについて意味の乏しいコメント。副題の「思いやり」に期待したが日本のパターン化した社会思考構造への踏み込みもなく退屈な本だった。2025/07/21
ののたま
16
会話の基本ではあるが、相手に合わせ、話を引き出せるような聞き方が重要、否定する場合もやんわりと。分かってはいるが中々難しい。▲政治家の話し方の例示、分析は浅くはあるが、分かりやすかった。聞き手(支持者)によって受取り方は異なるかもしれないが、伝わりやすい話し方の特徴は分かった。▲後半は飛ばしてしまったが、自分の話し方の意識は再認識できた。2025/09/09
大先生
15
科研費で行った研究成果の一部をまとめた本です。そういう本だという前提で読んだ方がいいですね。もともと読み物としての面白さを追求して書かれた本ではないということです。とはいえ、日頃当たり前に出来ていると思っているコミュニケーションについて改めて考えるのは面白い。コミュニケーションは伝えることよりも、実は聞くことの方が大切だということが分かりますね。雑談も非常に大切な働きをしているわけですから、明日からは堂々と職場で雑談しましょう(笑)ところで、私はすぐに反駁してしまうので、全く優しくないです(汗)2025/07/14