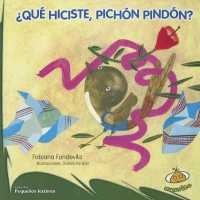出版社内容情報
私たちの周りでは当たり前のように外国人たちが働き、暮らしている。もはや日本は世界的な「移民大国」となっている。しかし、その受け入れは決してフェアなものではなかった。雇用、家族形成、ことば、難民……彼ら彼女らが生きる複雑で多様な現実を描き、移民政策の全体像と日本社会の矛盾を浮き彫りにする。
内容説明
私たちの周りでは当たり前のように外国人たちが働き、暮らしている。もはや日本は世界的な「移民大国」となっている。しかし、その受け入れは決してフェアなものではなかった。雇用、家族形成、ことば、難民…彼/彼女らが生きる複雑で多様な現実を描き、移民政策の全体像と日本社会の矛盾を浮き彫りにする。
目次
第1章 「移民国家」日本へ―なぜ、いかにして、を考える
第2章 外国人労働者の受け入れと日本
第3章 外国人労働者の就労の現在
第4章 定住、外国人労働者から移民へ
第5章 差別、反差別、移民支援
第6章 多文化共生の社会への条件
著者等紹介
宮島喬[ミヤジマタカシ]
1940年生まれ。お茶の水女子大学名誉教授。専門は国際社会学。東京大学大学院社会学研究科博士課程中退。お茶の水女子大学教授、立教大学教授、法政大学教授を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
73
コンパクトな本ながら、現在の日本における外国籍をもったり外国出自の人々が制度的、社会的にどのように扱われているかの見取り図を提供している。少子高齢化の中、労働力、とりわけ現業労働力がひっ迫する日本は、外国出自の人たちの労働力に30年近く依存する傾向を高めてきた。しかしそうした人々は、よく知られる技能研修生や留学生のような「サイドドア」からの受け入れであり、本書ではそれを「フロントドア」から受け入れ、共生できる実質を制度的にも社会的にも作るべきとする。また、日本の難民受け入れについても厳しい指摘をしている。2022/11/29
tamami
49
私が住む田舎のコンビニやスタバにも、外国人と思われるスタッフがいて、懸命に働いている姿が常態化している一方で、一次・二次産業における研修生を中心とした外国人労働者の実態についても広く認知されるようになって久しい。本書では現在300万人を数えるに至った、日本の移民について、歴史や受け入れの実態、とりわけ就労や定住、言葉や家族の問題等、多方面に渡る問題意識のもと、具体例を織り込みながら詳述される。「移民政策」がもたらした現状と課題を知ることで、我々一人一人に「移民問題」に向き合うことの大切さを示唆してくれる。2023/02/02
綾(りょう)
15
著者は国際社会学を専門とする大学教授。最近、フランスで起きた暴動や川口市でのクルド人の問題を見ていると、移民について否定的に感じがちだ。だが、日本での移民に関する法整備が整っていないことも事実。この本では、移民についての基礎的な知識がのっているため、移民について知るきっかけになる本だと思う。2023/09/27
coolflat
14
60頁。技能実習生として労働者の募集、採用、準備研修、受け入れの過程には不透明な要素がある。公私機関の区別は明瞭ではない団体が実習生希望者から、斡旋、紹介、渡航準備研修のための多額の手数料を徴収し、保証金まで積ませることがある。そのため彼彼女らはしばしば驚くほどの借財を負って来日している。技能実習制度は国の制度設計による外国人労働者受け入れのしくみなのに、なぜ現地のそうした営利団体にも近い仲介・斡旋機関を排除しなかったのか。政府の責任が問われる。2025/12/17
tharaud
10
2022年の刊行。ウクライナ戦争やコロナパンデミックの影響にも言及されている。日本はすでに移民国家といえる状況になってるが、制度も人々の認識も十分ではない。「外国人労働力」云々を論じる前に、人権を保障する法制度の整備が急務であることがわかる。「研修」「留学」を建前とした就労者という「サイドドア」からの受け入れが、結果的に社会保障を受けられず貧困に陥る移民を生み出しており、「フロントドア」からの受け入れを進める必要があるという指摘はもっとも。2025/07/05
-
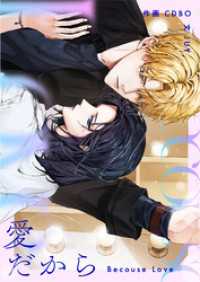
- 電子書籍
- 愛だから【タテヨミ】第46話 picc…
-

- 電子書籍
- 十三歳の誕生日、皇后になりました。【分…