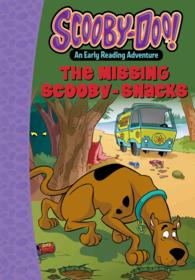出版社内容情報
現代におけるデモクラシーの危機。それは、世界の大規模な変容の反映である。この危機を生き抜く鍵は、人々が織りなす「オピニオン」なる曖昧な領域と、その調達・馴致の長い歴史にある。国家にかかわる思想史をオピニオン論で再解釈することで、大きく変化しつつある政治の存立条件を未来まで見通す、斬新な政治学入門。
内容説明
現代におけるデモクラシーの危機。それは、世界の大規模な変容の反映である。この危機を生き抜く鍵は、人びとが織りなす「オピニオン」なる曖昧な領域と、その調達・馴致の長い歴史にある。国家に関わる思想史をオピニオン論で再解釈することで、大きく変化しつつある政治の存立条件を未来まで見通す、新しい政治学入門。
目次
第1章 オピニオンとは何か
第2章 中世のボディ・ポリティック―「死なない王」のオピニオン
第3章 近代主権国家の誕生―「死なない国家」のオピニオン
第4章 革命が生んだ新たな祖国―オピニオンは国家のための死を求めるか
第5章 現代の国家―ナショナリズムとオピニオン
第6章 国家の未来―政治の死?不死の人間?
著者等紹介
堤林剣[ツツミバヤシケン]
ケンブリッジ大学博士号。現在、慶應義塾大学法学部教授
堤林恵[ツツミバヤシメグミ]
東京大学大学院総合文化研究科後期博士課程中途退学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
12
新書にしては扱うテーマが広すぎてしんどいなと思ったら、後書きで大学の講義をベースにしているとあり納得。力点は「オピニオン」よりも、「生と死」の方にあると私は感じた。国家の死と不死、王の死(2つの身体)、そして国民の死から、テクノロジーの進歩による人間の不死へという論の進み方はとても面白い。思想史であるとともに政治史。2021/07/05
ふみあき
12
ナポレオンは晩年、英雄が一人奮闘しようとも「状況とオピニオンが味方してくれなければ、どんなやり方をしようが無駄なのだ」と悟った。その政治思想史上の真理について、ヒュームの「統治の第一原理について」、ボダンの『国家論』、ホッブスの『リヴァイアサン』、ボシュエの「王権神授説」、ロベスピエールの「理神論」、シュミットの『政治的なものの概念』などをテキストに語られる。オーソドックスな本だと思うが、終章だけは趣が異なり、テクノロジーの進歩がオピニオンを必要としなくなるディストピア(ユートピア?)について論述される。2021/05/01
politics
6
国家理論の生成・展開をオピニオン論と正統性理論で辿る政治思想史。王国・国王が「死なない体」を手に入れ、その後、宗教論争を経て国家自体が死なない国家へと変貌を遂げて行く。終章ではテクノロジーの進歩がオピニオンの効用を妨げる可能性を示唆している。若干、話が広がりすぎているようではあるが、オピニオン調達のもと、民主主義を維持していくことが長い歴史の中で築かれて行ったことがよく解る。 2024/03/12
八八
6
ある一つの政治思想が社会において浸透しているのは、社会が強固にその思想を信じる人々によってのみ構成されているからではない。どちらかと言えば"何となく信じている”という人が多いからである。本著はそれをオピニオンと定義して、ホッブスやボダンなどの近世の政治思想からフランス革命、ナショナリズムといった現代までの様相を描く。各時代においてどのように政治思想が議論され、オピニオンとして人々に浸透し社会を構築したのかを丁寧に纏めた良著である。2022/03/27
(k・o・n)b
5
数で勝る被支配者は、なぜ常に少数派である支配者に従うのか。それは「何となく従うべき」という共通感覚=オピニオンがあるから。前半部では、王権神授説やら人民主権やら数々のオピニオン獲得のための言説=正当性理論が語られてきたことが解説される。ここまではまだオーソドックスな政治思想史っぽいが、最終章では打って変わっていきなり未来の話に。オピニオンが重視されない人々に対してなら権力は幾らでも冷酷になれる、という主張は本邦の入管問題等の状況を見ると頷けるが、死の克服のくだりは突拍子もない話に聞こえよく飲み込めず…。2021/06/21
-

- 電子書籍
- NAILEX 2022年10月号
-

- DVD
- ミッシング44