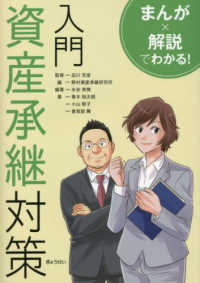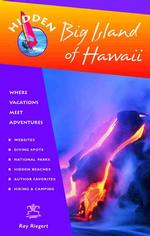出版社内容情報
歴史・思想・作品・技法を縦横に読み解く.矢代幸雄の名著『水墨画』から半世紀,あらたな水墨画への道案内.
内容説明
墨と、筆と、紙―この、シンプルな素材から生みだされてきた「モノクロームの世界」は、果てしなく豊かで、奥深く、そして愉しい。東アジア独自の筆墨文化に広く目くばりしながら、水墨画の歴史と思想、作品と技法を縦横無尽に読み解く。矢代幸雄の名著『水墨画』から半世紀、水墨画へのあらたな道案内。
目次
第1章 水墨画とはなにか?
第2章 水墨の発見
第3章 水墨画の存在様式
第4章 イリュージョニズムの山水画
第5章 水墨画がやってくる
第6章 詩書画の世界
第7章 「胸中の丘壑」から「胸中が丘壑」へ―水墨表現のさまざま
著者等紹介
島尾新[シマオアラタ]
1953年、東京都生まれ。東京大学大学院修士課程修了。東京国立文化財研究所・独立行政法人文化財研究所、多摩美術大学をへて、現在、学習院大学文学部教授。専攻は日本美術史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サケ太
23
良書。水墨画とは何か。西洋の絵画との違いや、その歴史を技術や人物、作品とともに解説してくれる。東洋の芸術は西洋のものと比べて劣っている部分(遠近法の有無)があると思い込んでいたが、実際は西洋の芸術よりも先取りされていたものも多く、見方が変わった。どういった表現があるのか。画の題材についても学べたので、実際の作品を見てみたいと感じた。2020/02/10
さとうしん
17
語り口が軽く、入門書として取っつきやすい。筆と墨で描いたものは何でも水墨画なのか?中国から伝来する以前に日本に水墨画は存在しなかったか?書と画との境界は?という本質論的な議論がおもしろい。第3章で紙水墨の科学分析的な話を展開しているのは今風かもしれない。水墨画とは何かという疑問から、更に何が芸術なのかという疑問に発展させてくれる書となっている。2019/12/29
崩紫サロメ
16
ありそうでなかった水墨画の論理的な入門書。水墨画という概念自体が近代的なものであり、言葉として普及したのは主に戦後。従来中国では「詩書画三絶」と言われた通り、詩と書と画は一体のものであり、その中から絵画を切り離していったのが近代である。故に、万能の天才と言うべき王維のような人物についても、「個としての芸術家」ではなく、「王維が天意に感応した」と捉えられる。芸術論寄りに読んだが、具体的な画法についての解説も面白く、いろいろな人の期待に応えられる良書だと思う。2020/03/09
C-biscuit
16
新品購入。水墨画の本であるが、水墨画の歴史というかそもそも水墨とは何かというような本である。単に墨で書いた絵を指すのかとも思っていたが、色のついたものや文字が入ったものなど、単なる絵ではない深さがある。筆と紙は当然のように作品に影響するが、なんと水についても違いがあるようで、実験的な資料や中国と日本の水の違いなども書かれていた。本当に奥が深いと感じる。扇子に描いた絵を剥がして掛軸にするなども面白い。最近はアプリでも気軽に絵をかけるものもあり、本格的な準備をせずにとりあえず、挑戦できるのはいい時代である。2020/02/18
六点
13
軽妙な語り口による、水墨画の歴史と、その理論、展開を大掴みに理解できた。書が草書により絵画感を獲得し、その逆に書が篆書を遡り、象形文字に逢着して、絵画性を獲得したというところに書と文と画の相互乗り入れ感を覚えた。まぁ、文字を絵画に取り込むのは蕨手など日本画の得意とするところであったのだ。文化の取捨選択、再統合という日本文化の強靭な遺伝子と言うか、大国との付き合い方の一つの典型と言えよう。しかし、通覧して思うのは古典の知識が和漢両方ともに必要で、それが前提となる、絵画の理解は。古典不要論は、文化的自殺だね。2020/09/06