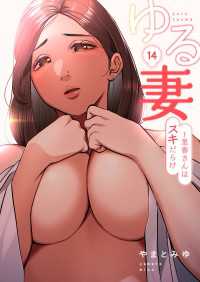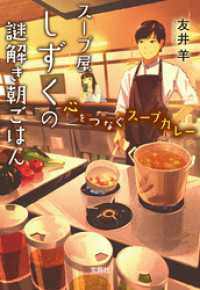出版社内容情報
放送倫理とは何か.放送の自由をどう守るか.「放送と通信の融合」の時代を見据えて,その公共的役割を考える.
内容説明
権力から独立した放送は民主主義の基盤であり、国民の知る権利のためのインフラである。どんな歴史的教訓から今日の放送制度がつられたのか。放送倫理とは何か。自主・自律の取り組みで放送の自由を守れるか。技術革新に伴うメディア環境激変の中、「放送と通信の融合」の時代を見据えて、その果たすべき公共的役割を考える。
目次
第1部 放送制度の歴史と放送の自由(放送のはじまりと不自由な放送がもたらしたもの;占領下の放送法誕生―新憲法制定と電波三法;NHKと民放の二元体制成立とテレビ放送の開始;放送制度の変遷;放送の自由に対する干渉)
第2部 憲法から見た放送の自由(放送法四条と表現の自由;自主・自律の制度としての放送法;最高裁判所の見解)
第3部 自主・自律の放送倫理の実践(番組審議会;BPOによる放送倫理の実践;欧米の放送制度との比較から見た日本の放送制度)
著者等紹介
川端和治[カワバタヨシハル]
1945年、北海道生まれ。1968年、東京大学法学部卒業。現在、弁護士(第二東京弁護士会会員)。第二東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長を歴任。2007年から2018年まで、BPO(放送倫理・番組向上機構)放送倫理検証委員会委員長をつとめる。2018年、放送批評懇談会より、自主・自律的な放送倫理の仕組みを放送界に定着させることに貢献したことに対して「第9回志賀信夫賞」を贈られた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
1.3manen
おおにし
崩紫サロメ
小鳥遊 和