出版社内容情報
哲学者フーコーは,著作ごとに読者を新たな見知らぬ世界へと導く.その絶えざる変貌をたどる.
内容説明
ミシェル・フーコー(一九二六‐八四)は顔を持たない哲学者だ。今の自分にとって「正しい」とされることを徹底的に疑いぬき、自己を縛り付けようとする言説に抗い、危険を冒してでも常に変化を遂げようとした。だからこそ彼の著作は、一冊ごとに読者を新たな見知らぬ世界へと導いていく。その絶えざる変貌をたどる。
目次
序章 顔を持たぬために書くこと
第1章 人間学的円環―『狂気の歴史』とフーコーの誕生
第2章 不可視なる可視性―『臨床医学の誕生』と離脱のプロセス
第3章 人間の死―『言葉と物』
第4章 幸福なポジティヴィスム―『知の考古学』
第5章 「魂」の系譜学―『監獄の誕生』と権力分析
第6章 セクシュアリティの歴史―『性の歴史』第一巻『知への意志』
第7章 自己をめぐる実践―『性の歴史』第二~四巻と晩年の探究
終章 主体と真理
著者等紹介
慎改康之[シンカイヤスユキ]
1966年、長崎県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程中途退学。フランス社会科学高等研究院(EHESS)博士課程修了。現在、明治学院大学文学部フランス文学科教授。専攻は20世紀フランス思想(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
50
フーコーの人となりの描写を回避して(写真も最初の1枚)、テクストの読解に特化したのは良かったのではないかと思います。その迂遠さにしばしば見失いますが、本書に戻ってきて大掴みにでも確認して、前後の著作との関連付けもできるため、これから折に触れて参照するのではないかと思います。フーコーという人物がある統一的な像を描き、我々が客体化した像から産出される言説に矛盾が無いかどうか、その様に構成された知とそこから生みだされる権力の循環からの離脱として、何よりフーコーの仕事はあったという理解からこの本は始まっています。2021/05/26
1.3manen
48
フーコーとの出会いは、佐藤幸男先生の地域国際関係論で出てきた『言葉と者』(本書では第3章)であった。好奇心とは、自分自身から離脱することを可能にしてくれるもの(4頁)。人間が描写、葛藤を乗り越えることができないとき(17頁)。富の生産、流通、蓄積に参加できない人々、労働で無力な人々が、社会における最大の悪徳を示す人々として閉じ込められた。監禁措置(23頁)。メルロ=ポンティは、高等師範学校の心理学復習教師として、後にはソロボンヌの心理学教授として、学生時代のフーコーを大きく魅了していた(53頁)。2021/05/28
yutaro sata
35
自明とされてきたものの考え方に対して疑いをかけていく。そうすることにより、自身が囚われていたものから脱出可能となり、同一であり続けることを拒否することが出来る。 フーコーの、おそらくかなり分かりやすく書かれている入門書であると思いますが、それでも難しくて3回は読みました。 ここから『言葉と物』に行きたいところですが、この入門書を読む限り、まずは『カントの人間学』に入った方がよいと感じたので、そちらへ行きます。2023/09/29
ケイトKATE
32
フーコーの著作を購入したものの、読むのに二の足を踏んでいると、読メユーザーの方から本書をお勧めされ読んだ。慎改康之のフーコー本は、フーコーの主要著作をコンパクトに解説している。フーコーという人は、常に自分自身から抜け出し、同じのままであり続けないように思考し続けた。本書を読んだのをきっかけにしてフーコーの著作を読んでみようと思う。2020/11/30
きいち
30
常にこれまでの自己の考え方から脱け出そうとしてきたフーコーの姿を描き出してくれることで、あらためて、フーコーがこれからの哲学者なんだと感じさせてくれる。気になっていた「講義集成」や「思考集成」、読まねば。◇なんと!フランスでは『性の歴史』に4巻が出ていたのか。今翻訳進んでいるのかな。◇それぞれの時期の主要作品をわかりやすく読み解くさまはまさに入門書。「なぜ突然ギリシャ・ローマ?」のあの疑問にも明快に応えてくれる。この先は自分で読んで考えろ、と。原典(翻訳しか読めないけど)行きたくなる、いい入門書だ。2019/12/29
-
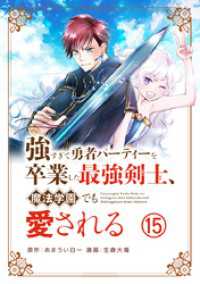
- 電子書籍
- 強すぎて勇者パーティーを卒業した最強剣…
-
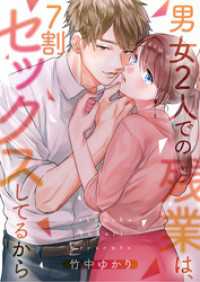
- 電子書籍
- 【フルカラー】男女2人での残業は、7割…
-

- 電子書籍
- 魔法少女にあこがれて ストーリアダッシ…
-
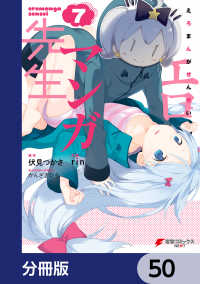
- 電子書籍
- エロマンガ先生【分冊版】 50 電撃コ…
-

- 和雑誌
- 新潮 (2025年4月号)




