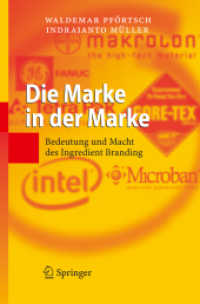出版社内容情報
「賢才」か、「物狂」か。『太平記』でも評価の二分する後醍醐天皇とは、一体何者だったのか? 鎌倉幕府倒幕から南北朝争乱へ、日本社会の大きな転換を引き起こした天皇の目指したものを、後世への大きな影響も視野に読み解く。
内容説明
「賢才」か、「物狂」か。鎌倉幕府崩壊から南北朝動乱へ、日本社会の大きな転換を引き起こし、『太平記』でも評価の二分する後醍醐天皇。彼がめざした「新政」とは何だったのか?宋学への傾倒、密教との関わり、「無礼講」の実際、そして後世への影響などに目配りしつつ、後醍醐が問うた「天皇」のあり方を読み解く。
目次
序 帝王の実像と虚像
第1章 後醍醐天皇の誕生
第2章 天皇親政の始まり
第3章 討幕計画
第4章 文観弘真とは何者か
第5章 楠正成と「草莽の臣」
第6章 建武の新政とその難題
第7章 バサラと無礼講の時代
第8章 建武の「中興」と王政復古
著者等紹介
兵藤裕己[ヒョウドウヒロミ]
1950年名古屋市生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。文学博士。現在、学習院大学文学部教授。専攻は日本文学・芸能論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
60
後醍醐天皇を『太平記』での記述を通して解説しているので、日本史の研究者とは多少異なった側面から後醍醐天皇について考察している。宋学への傾倒から倒幕へと向かっていくが、宋のように貴族が没落し、士大夫(儒教知識人)が台頭したということが日本の南北朝時代には起きなかったので、建武政権は短命で終わってしまった。また江戸時代に「大日本史」が南朝を正統としたのは新田源氏の流れをくむとされている徳川家の支配を正当化するものであったと指摘している点は興味深く感じた。2024/12/27
浅香山三郎
22
「あとがき」にもあるが、歴史と文学のいはゆる専攻・分野の壁を一旦無くして後醍醐の「史実」と「イメージ」の双方を丁寧に論じ直す。網野批判としての第4章を媒介にして、後半は『太平記〈よみ〉の可能性』の著者だけあつて鮮やかな叙述で、後世の後醍醐像・南朝像の形成を読み解く。2018/11/11
内藤銀ねず
22
読んで「あっ」と思ったのが、作中に『言表』とか『言説〈ディスクール〉』とあったこと。本当にさりげなく、絶妙なページに。ということでこの本はフーコーの方法論を借りて後醍醐天皇にまつわるあれこれを論じていたのでした。そのあれこれの中身は、当時の人々の共通認識だったり、後醍醐天皇を論じる人々の方法論だったりと、とても幅が広いです。この本を読む前に、中山元『フーコー入門』(ちくま新書)を読んでおくといいですよ。よくある歴史系の新書とはひと味もふた味も違う(それが作者の意図だと思う)歯ごたえのある本でした。2018/09/12
魚京童!
20
「玉骨はたとひ南山の苔に埋もるとも、魂魄は常に北闕の天を望まむと思ふ」2026/01/31
さとうしん
13
真言密教への傾倒は父・後宇多法皇の影響であること、文観の人物像の再評価、その「新政」の思想的背景として宋学の受容があったといった指摘を通して、「異形の王権」とされてきた後醍醐天皇のイメージとその政治の評価の修正をはかる。最終章の後醍醐天皇の企てた「新政」が近代日本を呪縛したという発想は面白いが、その詳論をもう少し読みたかった気もする。2018/05/07