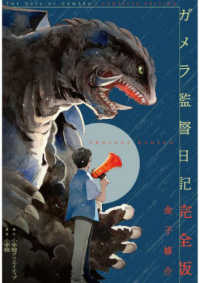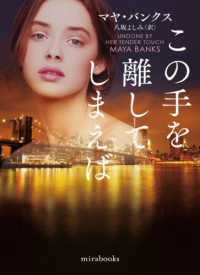内容説明
「学び」とはあくなき探究のプロセスだ。たんなる知識の習得や積み重ねでなく、すでにある知識からまったく新しい知識を生み出す。その発見と創造こそ本質なのだ。本書は認知科学の視点から、生きた知識の学びについて考える。古い知識観―知識のドネルケバブ・モデル―から脱却するための一冊。
目次
第1章 記憶と知識
第2章 知識のシステムを創る―子どもの言語の学習から学ぶ
第3章 乗り越えなければならない壁―誤ったスキーマの克服
第4章 学びを極める―熟達するとはどういうことか
第5章 熟達による脳の変化
第6章 「生きた知識」を生む知識観
第7章 超一流の達人になる
終章 探究人を育てる
著者等紹介
今井むつみ[イマイムツミ]
1989年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。1994年ノースウェスタン大学心理学部Ph.D.取得。現在、慶應義塾大学環境情報学部教授。専攻は認知科学、言語心理学、発達心理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
142
新書の割には内容が非常に学術的な感じでしっかりしている本ではないかと思いました。どちらかというと軽く読めるハウツー的な本をイメージしていたのですが、内容がかなり専門的な感じです。またたしかに私などは古い知識観にとらわれていると感じることがあります。人前でしゃべるときなど特に感じます。この本を読んで少しは今後の学びの在り方を少しは模索できた気がします。2016/10/30
esop
73
自分で問題を発見し、考え、解決策を自分で見つける」という「学習力」そのものである/究極の学習というのは「自分をきちんと客観的に知る」(メタ認知)と「相手の気持ち、考え方、感情を知る」(思いやり)である/行間を補うために使う常識的な知識、これを心理学では「スキーマ」と呼んでいる/人は自らスキーマをつくり、そのスキーマのフィルターを通してものごとを観察し、解釈し、考え、記憶する。ただし、スキーマは経験的につくられた、いわば「思い込み」でもある。そのため、いつも正しいとは限らない2024/10/04
TS10
72
私たちが情報を処理し、作業を行う際、多くの場合は共通の神経回路が使われているが、特定の作業を繰り返し行い、神経細胞にその記憶が蓄積されてくると、その認知及び作業に特化した独自の神経回路が形成されるようになる。これをスキーマと呼び、良くも悪くも人類の認知機能を規定していると説く。本書では、将棋棋士の羽生善治氏の発言が多く引用されているが、将棋には次の手を素早く思いつく「直観」と大局を見通す「ひらめき」とが存在するという指摘が取り分け興味深かった。2025/07/26
rigmarole
71
印象度A-。著者も「はじめに」で断っているように、本書は即効性のある勉強術のハウツー本ではありません。しかし人間の学習過程を認知科学・発達心理学の研究成果や達人のエピソードに基づいて様々に分析し、その結果からよい学びとは何かについて論じており、仕事上も、個人的にも、非常に示唆に富む本でした。畢竟するに「学ぶ力」とは、知識の断片を効率的に蓄積する能力ではなく、知識のシステムや理解の枠組み(スキーマ)を構築し修正する能力であるということ。そのための直感と批判的思考は車の両輪であるとの主張にも大いに同意します。2021/04/27
とくけんちょ
59
いわゆる賢い人になるためにはどうしたらいいのか。学びについて考えてみようと手にとった。行間を補うための常識的な知識、スキーマというみたいだが、このスキーマと学びについての関連性は、なるほどと思った。赤ちゃんが母国語を習得するプロセスやはたまた熟達することで脳自体の働きはどうなるのかといった興味深いところがまとめられており、楽しめた。タイトルは固いが、読みやすい。残念ながら熟達に近道はないみたい。2023/02/18