内容説明
大化改新前夜、クーデターによる暗殺をきっかけに「滅亡」したとされる蘇我氏。仏教導入をすすめ、推古天皇の信頼も厚く、「大臣」として政権を支えた蘇我馬子を筆頭に、ヤマト王権の紛れもない中心であった一族は、なぜ歴史から姿を消したのか?その後の藤原氏の台頭までを視野に、氏族からみた列島社会の変化を描く。
目次
1 氏の誕生―氏の名を名のる(王の名をめぐって―中国の史書から;「倭の五王」の姓と名;大伴氏と物部氏―「職能」を名のる氏)
2 蘇我氏の登場(葛城氏と蘇我氏;蘇我氏の系譜をたどる;列島の開発と蘇我稲目;仏教の導入と馬子)
3 発展と権勢の時代(推古女帝の即位;推古朝における馬子の活躍;飛鳥の地と蝦夷・入鹿;蘇我氏と「天皇」)
4 大化改新―蘇我氏本宗の滅亡(東アジアの情勢からみた「乙巳の変」;大化の改革と蘇我倉山田石川麻呂;生き延びる蘇我氏傍系―七世紀後半の蘇我氏;石川氏の活躍)
5 蘇我氏から藤原氏へ(藤原氏の誕生と不比等―名負いの氏からの離脱;律令法と氏・氏族;奈良時代と藤原氏)
著者等紹介
吉村武彦[ヨシムラタケヒコ]
1945年朝鮮大邱生まれ。京都・大阪育ち。1968年東京大学文学部国史学科卒業、同大大学院人文科学研究科博士課程国史学専修中退。現在、明治大学文学部教授。専攻、日本古代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
39
本書のテーマ:蘇我氏という氏族の興亡に沿いつつ、ヤマト王権の頃から中臣氏=藤原氏が台頭する奈良時代までの歴史を追うこと(10頁)。重要なことは、系譜に連なる地名を名のる臣系氏族が、系譜を自らが天皇に仕え奉る根拠としていた点(69頁)。天皇は代替わりごとに、仏教の需要の是非を群臣に諮問している。即位ごとに、任命するかたわら、仏教の受容や新羅遠征などの重要政策について、群臣に審議を求めるのが当時の慣行だったため(94頁)。蘇我氏の特徴:娘を天皇に嫁がせ、外戚の地位を保持(149頁)。2016/05/31
slider129
36
表題からして蘇我氏が歴史上の舞台にどのように現れて消えていったかを、面白おかしく解き明かしてくれると思いながら読み始めてみたが、なんか小難しい本だったなw。それでも蘇我氏を中心に日本のヤマト王権の神話の頃から奈良時代の藤原氏の台頭までの歴史が学べる情報量の多さは満足に値します。ことに氏姓制度について丁寧すぎるほどに書かれていたのは、あとがきを読んで「そういうことか」と的を得ました。八色の姓と共に氏と姓と苗字の違いが理解できただけでも本書を読んだ価値有りです。しかし古代史の権力闘争は謀略が渦巻く世界だね。 2017/10/23
ロッキーのパパ
26
評価は★★☆(満点は★★★★★) 蘇我氏の出自からいわゆる「大化の改新」後の蘇我氏の行方を通して、日本の古代史を概説している。興味の中心が蘇我三代にあったけど、それを扱ったボリュームが少ない。その点で興味とずれていた。2016/04/25
yamahiko
25
蘇我氏本によくある情緒的な表現を極力抑え、古文書に因る記述を繋ぎながら検証していく。岩波新書らしい一冊。2017/12/10
鯖
21
同時期に出版されたこちらも併せて読む。こちらは歴史の中で蘇我氏が果たした役割についてが多めかなあ。後書きで「ふじわらのみちなが」だけど「とくがわのいえやす」じゃない理由について、「藤原は氏だけど、徳川は苗字だから」と一文でさらっと説明されていた。同じ血脈をもつ氏が細分化し、日常的な呼称として苗字が生まれたから、氏のほうが枠として苗字よりでっかいでいいんかな。いえやすも公式文書では「みなもとのいえやす」になるし。2016/02/28
-

- 洋書
- Estações …
-
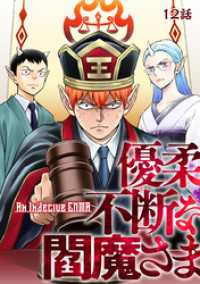
- 電子書籍
- 優柔不断な閻魔さま 12話 TRIUM…





