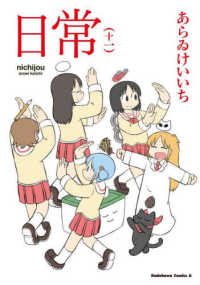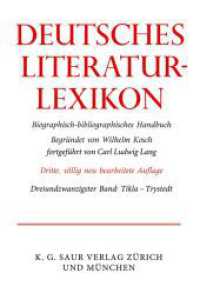内容説明
グローバル化のなか、人々や社会、国家や宗教などのアイデンティティの根幹に関わる文化的リテラシーを問われる場面が多くなっている。固有の文化とは何なのか?文化を政策に活用することの是非は?国内外の数多くの事例を紹介しつつ、観念論と政策論の双方の視点から、文化の新しい使い方、その危険性と可能性を考察する。
目次
第1章 グローバリゼーションは「文化」を殺す?(スーパーモダン;ポストモダン ほか)
第2章 台頭する「人間の安全保障」という視点(格差の再編成;新自由主義の論理と力学 ほか)
第3章 ソフトパワーをめぐる競合(ソフトパワーをめぐる狂想曲;パブリック・ディプロマシーの時代 ほか)
第4章 新しい担い手たち(政策的価値は「不純」か?;ガバナンスの新たな潮流 ほか)
第5章 理論と政策の狭間で(「離見の見」;構築主義 ほか)
著者等紹介
渡辺靖[ワタナベヤスシ]
1967年生まれ。ハーバード大学Ph.D.(社会人類学)。オックスフォード大学シニア・アソシエート、ケンブリッジ大学フェロー、パリ政治学院客員教授などを経て、慶應義塾大学SFC教授。専門はアメリカ研究、文化政策論。日本学術振興会賞、日本学士院学術奨励賞受賞。著書『アフター・アメリカ』(慶應義塾大学出版会、サントリー学芸賞、アメリカ学会清水博賞、義塾賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
39
文化とは教養から知識、信仰、信条、意識、言説、芸術、価値、道徳、習慣、伝統まで、広範。人間の安全保障やソフトパワーといった非伝統的な安保にも焦点を当てて考察した一冊(ⅺ頁)。グローカリゼーション:ロバートソンの概念で、普遍主義の個別化と個別主義の普遍化の相互作用(22頁)。一見、能動的な主体による実践そのものが、実は、構造を再生産し、強化しているのではないかという視点は重要(39頁)。2016/02/11
kaizen@名古屋de朝活読書会
22
#感想歌 #短歌 表現の自由と暴力境界線(border line)太く不鮮明参与観察(field work) 2017/03/22
Nobu A
10
図書館本読了。グローバル化が進む中、変容し続ける文化の在り方を問う。安全保障と言う視点を始め、様々な見方があり、政治や経済等と複雑に絡み合う。文化戦争と称し、国や地方の思惑も見え隠れする混沌とした世界。「ソフトパワー」と言う概念が興味深い。パブリック・ディプロマシーの成功事例の紹介。筆者のこれまでの足取りと本のタイトルに隠された意図。伝統文化、能楽の「離見の見」の精神に導かれた探究心と筆者の文化人類学や隣接分野からの視点や知見をいかに現代文脈に置き換え、次世代に継承していくかの叙述が深く心に残った。2017/10/31
nishi
9
文化とは営みであるという原点に立ち返りながら、昨今の文化同士の対立について疑問を投げかけている。文化とは本来分かち合うものであり、他者との境界線をつけるためのものではない。これが為政者によって境界線付けに利用されている現実を認識すべきであると感じた。その中で、暗黙的に引かれた境界線を可視化する芸術の重要性も大きいと思った。2021/11/21
やまやま
9
トランプ大統領出現前の執筆である。人間の安全保障の面から、ジョセフ・ナイ氏のソフトパワー論を展開して、発信側の器量の大きさを「メタ・ソフトパワー」と呼び、リベラルデモクラシーが権威主義の国々に対して優位に立つという議論を紹介している。ただ、コロナを経て、むしろ渡辺一夫氏の説く現状を内省的に捉える姿勢の方が、文化政策においても一層説得力を増しているように思える。留学生時代の生活経験が著作に多く影響していることは十分に感じられた。一方、文化政策では、国家の関与が少ない米国が優良モデルと評されるのは、さて。2020/07/03