内容説明
二〇一三年、首相の口から改憲要件緩和までが声高に叫ばれ再燃した改憲論議。なかでも重要な論点―改憲手続、憲法擁護義務、押し付け憲法論、国民の義務と自由、個人と家族、非武装平和主義、国民投票の功罪―を比較憲法の視点から丁寧に検討し、自民党改憲草案の危険性と今後の議論の在り方、日本国憲法の現代的意味を再確認する。
目次
序章 比較憲法から改憲を考える
第1章 改憲手続を比較する
第2章 「改正の限界」と憲法尊重擁護義務―九九条の意味
第3章 「押し付け」論再考―「自主憲法」とは何か
第4章 「国民は個人として尊重される」―人権規定を比較する
第5章 戦争放棄と「現実論」―平和的生存権と各国の平和条項
第6章 国民投票は万能か―国民主権原理
終章 「政治の論理」と憲法改正のゆくえ
著者等紹介
辻村みよ子[ツジムラミヨコ]
1949年東京生まれ。東北大学大学院法学研究科教授を経て、明治大学法科大学院教授。専攻は、憲法学、比較憲法、ジェンダー法学。法学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 宮廷墨絵師物語(コミック) 第20話 …
-

- 電子書籍
- GO WILD~獣人の恋は野性的~【タ…
-

- 電子書籍
- シークレットリベンジ~姉を殺したアイド…
-
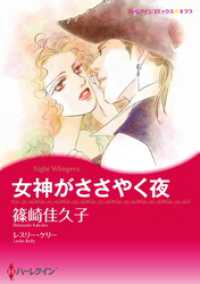
- 電子書籍
- 女神がささやく夜【分冊】 6巻 ハーレ…
-

- 電子書籍
- Berry's Fantasy 転生し…



