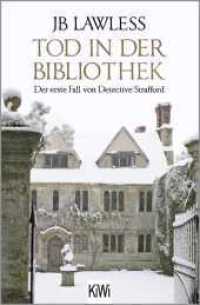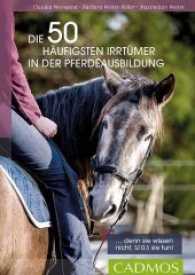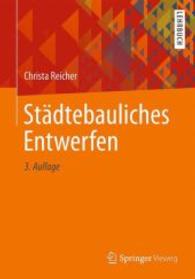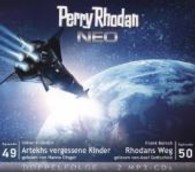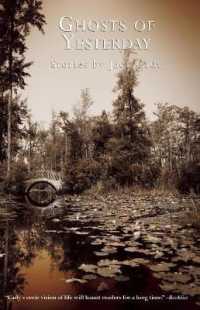内容説明
中央アジアを大きく蛇行する大河アムダリヤ。古来あまたの文明・文化がその岸辺で交差し、盛衰を繰り返してきた。その実像は、この半世紀、国際調査団によって、ようやく明らかにされつつある。若き日彼の地に魅了され、齢九十を超えて今なお現地で発掘調査に携わる著者が、青銅器時代からヘレニズムまでを視野に最新の研究成果を紹介する。
目次
序章 中央アジアの浮気な大河アムダリヤ
第1章 砂漠の風に消えた古代遺跡群―青銅器時代のアムダリヤ流域
第2章 「死ぬときは悔ゆることなかれ」―ヘレニズムの都市遺跡アイハヌム
第3章 アムダリヤに響くフルートの音―タフティ‐サンギンのオクス神殿
第4章 宗教改革ツァラトゥストラ―オクス神殿とゾロアスター教
終章 ヘレニズムの運命―シルクロードと中央アジア
著者等紹介
加藤九祚[カトウキュウゾウ]
1922年朝鮮に生まれる。1953年上智大学文学部ドイツ文学科卒業。専攻、北・中央アジア文化史。現在、国立民族学博物館名誉教授・創価大学名誉教授・ロシア科学アカデミー名誉歴史学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件