出版社内容情報
「近頃,日本人がヘタになっている!」と嘆く著者.ところが,遡れば江戸庶民文化から,ピカソ,岡本太郎,東海林さだお,立川談志まで,そこには脈々とヘタウマが息づいていたのだった.いまや芸術・芸能・サブカルチュア全般を席巻するヘタウマ文化.著者ならではの愉快痛快な筆が,日本文化を鮮やかに読み解く.
内容説明
「近頃、日本人がヘタになっている!」と嘆く著者。ところが、遡れば江戸庶民文化から、ピカソ、岡本太郎、東海林さだお、立川談志まで、そこには脈々とヘタウマが息づいていたのだった。いまや芸術・芸能・サブカルチュア全般を席巻するヘタウマ文化。著者ならではの愉快痛快な筆が、日本文化を鮮やかに読み解く。
目次
オモシロいって何だ
ヘタに賞だと?
ヘタウマとの出会い
糸井重里という思想
江戸テインメント
駄句のこころざし
談志が出来なかった芸
ピカソは途中でやめなかった
昔の物真似
モノマネ維新
シンボーひまなし
伊東四朗のユウウツ
山口瞳を呼び戻したい
日本文化を括ってみた
「日本漫画」が消えた
「文春漫画賞」かけあ史
ミスター・ヘタウマ・東海林さだお
著者等紹介
山藤章二[ヤマフジショウジ]
1937年東京に生まれる。武蔵野美術学校デザイン科卒業。広告会社をへて、64年独立。講談社出版文化賞(70年)、文藝春秋漫画家(71年)、菊池寛賞(83年)などを受賞、04年には紫綬褒章を受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
倍の倍のファイト倍倍ファイトそっくりおじさん・寺
とら
猫丸
Koki Miyachi
1.3manen
-
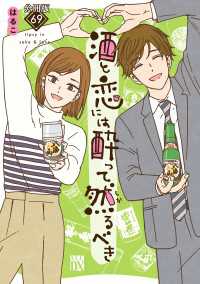
- 電子書籍
- 酒と恋には酔って然るべき【分冊版】 6…
-
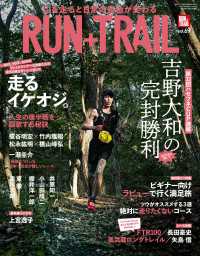
- 電子書籍
- RUN+TRAIL Vol.69
-

- 電子書籍
- 脇役だって黙っていられない!【タテヨミ…
-

- 電子書籍
- 蟻地獄【タテヨミ】 15 ニチブンコミ…
-
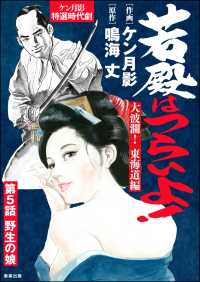
- 電子書籍
- 若殿はつらいよ!(分冊版) 【第5話】…




