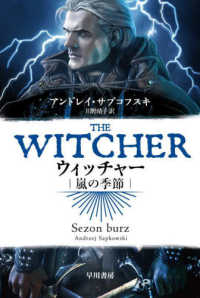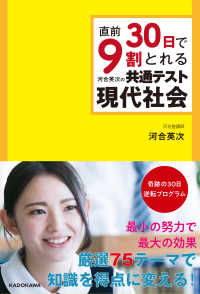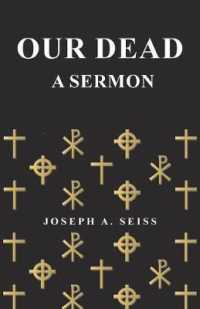内容説明
齋藤流「古典のすすめ」。ヤマ場を臨場感たっぷりに感じる「クライマックス読み」、映画やドラマなどから源流を辿る「さかのぼり読み」、読破にこだわらない「パラパラ断片読み」など、これまでにない、古典への近道を伝授。『論語』『罪と罰』から『夜と霧』『百年の孤独』まで、齋藤版古典五〇選(さらにおまけの五〇選つき)も詳しく紹介。
目次
第1章 古典力を身につける―今、なぜ古典力が必要なのか
古典を読むための十カ条(一通りの知識を事前に得る;引用力を磨く;さかのぼり読み―古典の影響を読み取る ほか)
第2章 活きた古典力―四人の先人のワザ(実践を支える古典力―渋沢栄一の論語の活かし方;孔子に学ぶ古典力―古典がつなぐ仲間意識;ゲーテに学ぶ古典力―偉大なものを体験する ほか)
第3章 マイ古典にしたい名著五〇選(作品世界にどっぷり浸かる;たった一冊の本が、時代を、社会を変えた;古代の世界は骨太! ほか)
著者等紹介
齋藤孝[サイトウタカシ]
1960年静岡県生まれ。1985年東京大学法学部卒業。東京大学大学院教育学研究科博士課程を経て、明治大学文学部教授。専門、教育学、身体論、コミュニケーション論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
103
時代も地域も異なるところで生まれ、百年、千年の時を超えて読み継がれて来た書物が「古典」で、これは書物であると同時にもはや「宝物」。多様性を代理体験するには古典は最強の一角ではないかと思いました。2024/06/22
月讀命
101
今書店に多く並んでいる本のうち、50年後にも店頭に並んでいる本は何冊存在するであろうか。100年後には果たしてどうだろうか。(100年先には紙の本という媒体が無くなって、電子書籍を超える得体の知れないものにとって変わられているだろうが・・)人類の先輩達が書きしるし、篩にかけられ、淘汰され残ったものが古典である。古典は時間と空間を超えて存在するものである。ドストエフスキーや紫式部、デカルト、漱石は未来に於いても永久不滅であろう。今流行の宮部みゆきや東野圭吾、三浦氏しをんが淘汰されるか否かが問われるところだ。2013/09/17
mitei
85
あまり古典を読まない私にはかなり興味深く読めた。2012/11/18
ずっきん
83
古典への近道伝授本。何から読めばいいのか、どう読めばいいのかわからないという人のための50選+50選他引用多数。カラマーゾフ語るのに『陽気なギャング〜』を引用するなどとっつきやすい。論語からドラッカーまでと幅広いため、思ってたより小説は少なかったな。古典はいいぞー面白いぞーと熱く語ってるとこが好感。『古典を読むための十カ条』も中々面白かったが、教養を身につけるためにはこう読むといいぞ的な感じも強い。絶対に合わないと思ってた中上健次を読んでみたくなったし、選書に刺激を与えてくれるね。2022/03/15
しゅてふぁん
50
古典を自分の血肉とする、なんて素敵なことだろう。古事記や聖書、ギリシア神話など読んでみたい古典はたくさんあるけれど、それらを読むための精神力と集中力が乏しくて…(;^_^A でもせっかく古典を読むことが習慣になってきたのだから‘古典力’とやらを鍛えて‘マイ古典’を増やしてみよう。2018/10/21
-

- 洋書電子書籍
- トランプ米大統領のツイッター言説分析<…