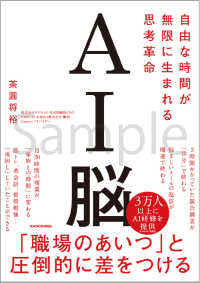出版社内容情報
ジャングルにそびえ立つ神殿ピラミッド,広場に林立する石碑,交易に用いられた黒曜石…….マヤ文明は中央アメリカに花ひらいた究極の石器文明だった.もはや謎と神秘のベールにくるみ論じる時代ではない.文字は王の事績を語り,考古学は貴族や農民の生活を明らかにする.マヤ文明の実像を,気鋭の考古学者が熱く語る.(カラー口絵一丁)
内容説明
ジャングルにそびえ立つ神殿ピラミッド、広場に林立する石碑、交易に用いられた黒曜石…。マヤ文明は中米の密林に花ひらいた究極の石器文明だった。もはや謎と神秘のベールに包んで論じる時代ではない。マヤ文字は王の事績を語り、考古学は貴族や農民の生活を明らかにする。マヤ文明の実像を、気鋭の考古学者が熱く語る。
目次
第1章 マヤ文明とは何か
第2章 マヤ遺跡を掘る
第3章 諸王、女王、貴族たち
第4章 農民の暮らし
第5章 宮廷の日常生活を復元する―アグアテカ遺跡
第6章 マヤ文明の盛衰は語る
著者等紹介
青山和夫[アオヤマカズオ]
1962年京都市生まれ。東北大学文学部卒業。ピッツバーグ大学人類学部大学院博士課程修了。人類学博士。「古典期マヤ人の日常生活と政治経済組織の研究」で日本学術振興会賞、日本学士院学術奨励賞を受賞。現在、茨城大学人文学部教授。専攻はマヤ文明学、メソアメリカ考古学、文化人類学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
397
マヤ文明に対する啓蒙書。私も本書に指摘されるまでは大いなる誤解をしていた。これは日本の世界史の教科書そのものもかなりいい加減であるらしく、またマスメディアの流す興味本位の情報によるところも多いそうだ。私の誤解の最たるものは、マヤもアステカもインカも共に中南米に花開いた古代からの文明であると思っていたこと。実はアステカ王国は1325年~1521年、インカ帝国は15世紀~1532年のものであり、紀元前1800年以前から栄えたマヤ文明とは比べ物にならないことであった。かろうじてマヤに匹敵するのは⇒2020/08/23
AICHAN
47
図書館本。中南米で栄えたマヤ、アステカ、インカは似たようなものだと漠然と思っていたが、実は大いに違うと知って驚いた。アステカ王国は14世紀から1世紀、インカ帝国は15世紀のものであり、紀元前1800年以前から栄えたマヤ文明とは比較にならないという。マヤのピラミッドはエジプトのそれと何らかのつながりがあると思っていたが、これもまったくの認識の誤りで、まるで接点はないとのこと。こういう間違いはどうも教科書やマスコミの伝え方に問題があるようだ。教科書もマスコミもマヤ文明の本当のところを正しくは伝えていないのだ。2021/04/09
翔亀
44
【始原へ43】<マヤ4>いずれ日本にもマヤ学者が生まれる、と石田英一郎が期待を込めて書いて(中公新書「マヤ文明」【始原へ40】)から50年、本書の青山は誕生した日本のマヤ学者の第一世代と言っていいだろう。しかし石田の想定とは違う形での登場かもしれない。アンデスの場合は<東大アンデス隊>が、いわば組織的に調査団を送り込んだ(石田はその第1回の団長)。その隊員がアンデス学者となった。同隊は途中、マヤの発掘も企画したが、グァテマラの内戦などにより断念して、アンデスでの調査を継続した。結局マヤは手掛け↓2021/08/18
syota
25
著者である青山先生のことはこの本で初めて知ったけれど、マヤ文明研究という日本人に馴染みの薄い分野で、これほど国際的に活躍されている方がいることにまず驚いた。20代から数十年間現地で遺跡調査にあたり、論文は英語とスペイン語で発表しているとのこと。マヤ文明は20世紀後半から飛躍的に研究が進み、従来の通説が書き換えられているそうだが、本書ではそれら最新の知見について、自身の研究成果を織り交ぜながら噛み砕いて記述されている。新書版の分量なので網羅的とはいかないのが残念だが、マヤ文明に関心がある方はぜひご一読を。2019/06/20
崩紫サロメ
22
マヤ文明は「四大文明」を中心とする古い歴史観においては軽んじられ、マスコミにおいては「謎と神秘の文明」としてわかっている部分が多いにも関わらず謎とされている。本書は考古学的な発見からマヤ文明について明らかになっている多くのことを紹介する、わかりやすい入門書である。近現代史の人間として興味深かったのが、グアテマラ内戦(1960~1996)の後、この地域で今の国境を越えた「マヤ人」という自意識が芽生えつつあるというあたり。2020/04/10