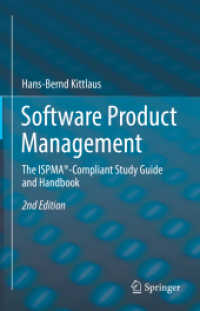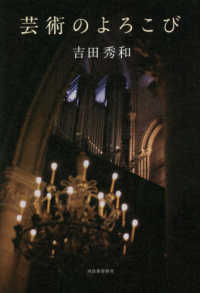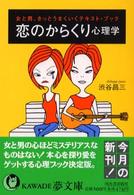出版社内容情報
インドで興った仏教は仏典の漢訳によって中国で広まり,朝鮮・日本にも伝えられた.そのような伝来の歴史の中で仏教に由来する数多くの漢語が誕生した.その中から,平等,世間,我慢,睡眠,道楽など日常生活で親しまれている50の言葉を取り上げ,その語源や意味について興味ぶかいエピソードを交えて説き明かす.
内容説明
インドで興った仏教は仏典の漢訳によって中国で広まり、朝鮮・日本にも伝えられた。そのような伝来の歴史の中で仏教に由来する数多くの漢語が誕生した。その中から、平等、世間、我慢、睡眠、道楽など日常生活で親しまれている五〇の言葉を取り上げ、その語源や意味について興味ぶかいエピソードを交えて説き明かす。
目次
序 仏陀
1 阿吽の呼吸(阿吽;阿弥陀 ほか)
2 前世の因縁(因縁;火車 ほか)
3 愛の煩悩(愛;行脚 ほか)
著者等紹介
興膳宏[コウゼンヒロシ]
1936年福岡県に生まれる。京都大学大学院博士課程修了。京都大学教授、京都国立博物館館長を歴任。現在、京都大学名誉教授。専攻は中国古典文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はやしま
23
日常使っている言葉の中で仏教由来のものについて解説された本。1語について4頁程度で語源のサンスクリット語、呉音・漢音への変化、元々の意味と現在使用している意味の違い、言葉に因んだ話などが盛り込まれている。雑誌連載をまとめたもので、岩波新書の赤本としては文章は平易だが内容は濃い。中国古典から落語、夏目漱石まで引用が幅広く楽しめる。漱石が多いのは著者がお好きなのか、漱石文学が近代日本語に果たした役割の大きさ故か。仕事の間や就寝前にゆっくり噛み砕くようにして読んでいたが、これからも折々に読み返したいと思う一冊。2017/12/21
ロッキーのパパ
10
仏教に関する言葉を50個選び、それらが、サンスクリット語から中国語に翻訳され、日本に伝わり、さらに現在ではどのような意味に変化しているのかを解説している。一つ一つのトピックスはエッセイ風であり、読みやすい。仏教由来の言葉が、意味の変遷はあるにしても、身近に浸透いるのかがよく分かる。ただ、「白居易は熱心な仏教徒・・・」とか「仏教に関する言葉は呉音を使う・・・」など同じエピソードが繰り返し出てくることが気になる。まあ、つまみ読みできるようにしているんだと好意的に解釈しよう。2011/10/26
もち
7
軽く書かれた読み物の感が強かった。エッセイ色のこい解説集。日本に強く関連づけられていて、中国にそこまで興味がないが、教養として仏教漢語をかじっておきたい、というかたには最適か。2016/04/26
gollum
1
仏教漢語を単に原典からの解説だけにしないところが筆者らしくていい。インド→中国→日本への言葉の伝来というよりも変遷として扱うのが楽しい。「寺」に追いやられたしまった「持」の立場のなさがおもしろい。2011/11/01
yo yoshimata
1
仏教を紀元にもつ漢語のあれこれを語るエッセイ集。面白かったけど難しかったです。でも、もっと勉強したいと思いました。2011/11/18