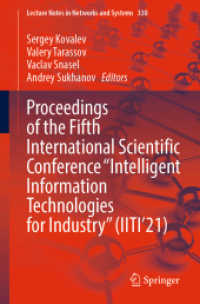出版社内容情報
デモクラシーがもたらす政治と社会の変容に透徹したまなざしを向けたフランスの思想家トクヴィル(1805-59)。彼は、その変化の本質に何を見、人間の未来をどう考えたのだろうか。現代に生きるその思想を丹念に読み解く。
内容説明
『アメリカのデモクラシー』『アンシァン・レジームとフランス革命』で知られるフランスの思想家アレクシス・ド・トクヴィル(一八〇五‐五九)。デモクラシーのもとで生じる社会と政治の変容に透徹したまなざしを向ける彼は、人間の未来をどう考えていたのか。生涯いだいていた憂鬱な感情を手がかりにして、今に生きるその思想を読み解く。
目次
序章 深さの肖像
第1章 憂鬱という淵源―デモクラシーへの問い、自己への問い
第2章 運動と停滞―平等の力学の帰結
第3章 切断と連続―アンシァン・レジームとフランス革命
第4章 部分の消失―分離する個と全体
第5章 群れの登場―新しい社会と政治の姿
第6章 形式の追求―人間の条件に向けて
終章 トクヴィルと「われわれ」
著者等紹介
富永茂樹[トミナガシゲキ]
1950年滋賀県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。現在、京都大学人文科学研究所教授、京都芸術センター館長。専攻は知識社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
103
トクヴィルの育った環境から彼の思想がどのようにはぐくまれていったのかを明快に説明してくれます。私も彼については何も知らずに大学の教養時代の政治学の先生が初めて紹介してくれました。その時には、ほとんど訳された本もなくノートをとるのに必死であったことだけを覚えています。「アメリカのデモクラシー」についてはあまり書かれていないので自分で岩波文庫をあたるほうがいいのでしょう。しかしながらトクヴィルについてこれだけ書かれているものはあまりなく力作だと思います。2015/11/07
ロビン
19
トクヴィルの評伝と思い読みだしたが、彼の生涯というより主著『アメリカのデモクラシー』『アンシャン・レジームとフランス革命』の内容を、両書に一貫するトクヴィルの思想を拾い出し、時にミシェル・フーコーやエマニュエル・トッド、またトクヴィルが愛読したというモンテスキューやパスカルの言葉を引きながら読み解いていくという本であった。アンシャン・レジームとフランス革命の間には断絶ではなく連続があること、民主主義社会では個人の矮小化と中央集権化が起こり、それが専制に繋がる為中間団体が重要であることなど、考えさせられた。2025/05/02
masabi
8
トクヴィルが得たデモクラシーの洞察を解説する。前回がアメリカ視察の足跡を追う作品だったので、今回は著作解説に重きを置いた本を読んだ。平等化と商業社会の発達によって絶えず競争し、身の丈を超えた野心を抱いては憂鬱と焦燥感に身を焦がす。競争社会の弊害は200年前から言及されていたと思うとトクヴィルの慧眼に唸らざるを得ない。デモクラシーと専制の考えをアメリカ視察以前から着想していたとの記述を見て驚いた。最終章は日本でのトクヴィル受容について。国家に対抗する結社、中間団体という見方が好感されたのだろうか。2024/11/26
hakootoko
5
中間の領域の消失。諸条件の平等。人口という概念と統計学の台頭。個人主義。過去を見つめ返さない未来志向。形式の喪失。焦燥。2020/10/15
onaka
5
アメリカのデモクラシーをヨーロッパに紹介した人という認識しかなかったが、まったくの誤解だった。諸条件の平等化は革命によって成し遂げられたのでなく、すでに専制性の中で進展していた。中央集権化と貴族の特権の弱体化、個人主義の台頭によって、個人は中間的な部分に属することなく直接国家という抽象につながる。同時に、官僚組織による行政の集権化がそれを下支えする。群衆の誕生と民主的な専制の可能性の検討、などなど、、後の社会学者たちの議論を先取りしていたエライ人だったのですな。2013/08/04