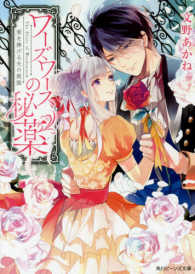出版社内容情報
中国の爆発的な経済発展、ロシアのエネルギー資源外交の展開、中央アジア諸民族の台頭、そして国境を越えるヒトとモノの奔流・・・・・。豊富な現地取材をもとに、いま沸き立つユーラシアに吹く風を伝え、その行方を考える。
内容説明
多極化する世界の中で、いまユーラシア全体が一つの地域として沸き立っている。中国の爆発的な経済発展、ロシアのエネルギー資源外交の展開、中央アジア諸民族の台頭、そして国境を越えるヒトとモノの奔流…。現地取材を重ねたジャーナリストが、この広大な一帯に吹く変革の風を伝え、そのダイナミズムの意味を考える。
目次
序章 ユーラシアの風に吹かれて
第1章 分割された島―ユーラシアの国境政治
第2章 ユーラシアを束ねる上海協力機構
第3章 新しいシルクロードが生まれる
第4章 中央アジアのダイナミズム
第5章 広がるユーラシア・パイプライン
著者等紹介
堀江則雄[ホリエノリオ]
1947年生まれ。東京外語大ロシア科卒。国立国会図書館勤務を経てジャーナリスト(ワシントン、モスクワ駐在)。現在、法政大学講師、ユーラシア研究所運営委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひかりパパ
7
著者はアメリカを通じて世界を見るという惰性から抜け出し、ユーラシアに目を向けることを提唱している。ユーラシアに新しい風が吹いていることが良く分かる内容である。この本が書かれたのが2010年でその後ユーラシアの主要な構成国であるロシアはウクライナの領土であるクリミア自治共和国とセバストポリ市の併合を強行した。このプーチンの横暴さはスターリン時代復活を連想させる。またもう1つの主要国中国は東シナ海と南シナ海で力による現状変更を目指す動きをしている。この両国の動きはユーラシアの胎動の流れを後退させるものなのか。2017/03/07
yearning for peace
2
BRICsやNEXT11の陰に隠れているが、中央アジアがじわじわと熱気を帯びてきている。国境線の最終画定(第1章)、上海協力機構を中心としたプレゼンスの向上(第2章)、パイプラインを配した新たな動脈や各国ナショナリズムの台頭など、ユーロセントリズムからの脱却を着々と進め、ネオ・ユーラシア主義からますます目が離せなくなってきている。2010/06/09
ゆきんこ
1
ユーラシアを政治的経済的に緩やかに束ねているのが、上海協力機構SCOだ・2001年6月成立・ロシア、カザフ、タジキスタン、キルギス、ウズベク8//scoの意義は、帝政ロシア、清時代から中ソ時代を含めて対立と緊張関係を続けてきたロシアと中国の両国が、その戦略的思惑を抱えながら政治的経済的パートナーシップを基軸に戦略的提携の道に踏み出したことにある。9//インド、パキスタン、イラン、モンゴルがオブザーバー加盟10//2022/10/24
ひとみ
1
ユーラシアについて全く何も分からなかったので、本書の入門的な易しい説明がレベルとして丁度良く、少し昔の本ではあるが非常に興味深かった。ユーラシア中央の各国について地政、宗教、資源など様々な要素に触れており、包括的に知識を得ることができた。旅行に行きたくなった。2022/03/16
はっちー
1
普段は中央アジアには目を向けないがこの本では中央アジアに迫っている。中央アジアはロシアと中国の脅威に常に晒されているが、友好的な面も大いになる。欧米一強の時代から多元的世界への変貌を示唆している。2017/02/11