内容説明
憲法改正とともに日本の今後を占う最大の焦点に浮上した集団的自衛権。その起源を検証し、戦後の日米関係においてそれがいかなる位置づけにあったのかを歴史的にたどる。そして今日の世界が直面する脅威の性格を冷静に見すえながら、集団的自衛権の行使による日米安保体制の強化という路線に代わる、日本外交のオルタナティヴを提起する。
目次
序章 憲法改正と集団的自衛権
第1章 憲章五一条と「ブッシュ・ドクトリン」
第2章 第一次改憲と六〇年安保改定
第3章 政府解釈の形成と限界
第4章 「自立幻想」と日本の防衛
第5章 「脅威の再生産」構造
第6章 日本外交のオルタナティヴを求めて
著者等紹介
豊下楢彦[トヨシタナラヒコ]
1945年兵庫県生まれ。京都大学法学部卒業。関西学院大学法学部教授。専攻、国際政治論、外交史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふろんた2.0
13
ふむふむ、なるほど。本書は集団的自衛権を行使することで孕む危険性を論じている。2007年初版のものなので、改版出ないかな。2014/07/18
かばお
9
難しい本だった、『メタルギア』シリーズであった戦争ビジネスのように核開発技術がアメリカなどの先進国から売り渡されているという指摘に心底驚いた。そんな売買、フィクションだけだと思っていたのに。2017/02/21
makio37
7
集団的自衛権の行使は名実ともに日本が米国の軍事戦略の枠内に組み入れられることを意味する。1950年代以来求められ譲歩し続けながらも「国際法上有、憲法上行使不可」の政府解釈をなんとか守ってきた。しかし、この十数年はアーミテージ・ナイらによる露骨な干渉を受け、一方で「一周遅れのネオコン」安倍が自ら進んで行使容認へ邁進している。「敵の敵は友」とする米国に振りまわされ、最後に"梯子を外される"のは目に見えている。提示される代替案も秀逸だ。日本の核武装はNPT体制の崩壊を意味することにも気付けた。2014/05/10
coolflat
7
集団的自衛権行使できないことによって、日本は米国に依存し続ける、のを米国は狙っていた。というのは、日本が集団的自衛権を行使して「米国を守る」よりも、米国が日本の基地を特権的に維持し続ける方が、米国の戦略にとって遥かに重要な意味を持っていたからだ。日本に基地提供義務を求め、米国は日本防衛義務を持つことで、憲法改正と集団的自衛権行使を棚上げにしていたのである。ところで昨今の集団的自衛権行使の解釈改憲は、安倍晋三の個人的野望もさることながら、米国の戦略転換も背景にある。ジャパンハンドラーによる「安保再定義」だ。2014/03/13
加藤久和
5
集団的自衛権は国連憲章51条を根拠に国連加盟国に認められる権利だが、日本においては憲法9条の存在によりその行使が制限されている。現安倍内閣はこの制限を突破すべく憲法改正に突き進むことが予想されるが、それは何のためか?安倍氏の目的は集団的自衛権の行使を可能にすることにより米国と対等に肩を並べ、米国に対し発言力を得ることにあるらしい。しかし著者の指摘によると現実は『日本の若者が在日米軍を防衛するために「血を流す」構造になっている』のであり、図らずも米日対等は皮肉な形で実現しているのである。増刷が待たれる1冊。2013/01/08
-
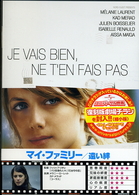
- DVD
- マイ・ファミリー/遠い絆








