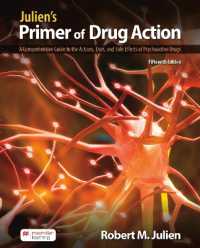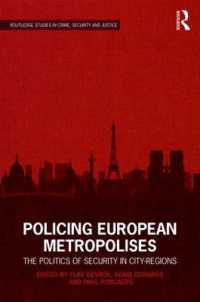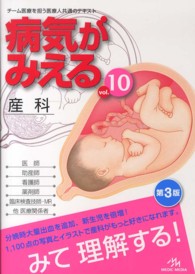内容説明
誰によって、いつ頃つくられたのか、本当に千一夜分の物語があったのか―いまや世界文学となった「アラビアンナイト」の成立事情は、謎に包まれている。まぼろしの「原典」探し、「偽写本」の捏造、翻訳による違いなど、成立から翻訳・受容の過程をたどり、異文化のはざまで変貌していく物語集の文明史的意味を考える。
目次
第1章 アラビアンナイトの発見
第2章 まぼろしの千一夜を求めて
第3章 新たな物語の誕生
第4章 アラブ世界のアラビアンナイト
第5章 日本人の中東幻想
第6章 世界をつなぐアラビアンナイト
終章 「オリエンタリズム」を超えて
著者等紹介
西尾哲夫[ニシオテツオ]
1958年香川県に生まれる。1987年京都大学大学院文学研究科博士課程修了。文学博士(京都大学)。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助手、同助教授を経て、人間文化研究機構国立民族学博物館教授、総合研究大学院大学教授。専攻、言語学、アラブ研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
340
『アラビアンナイト』に関する多角的な研究成果を一般向けに分かりやすく解説した啓蒙書。現存する写本としては「ガラン写本」として知られるものが最も古く、9世紀頃にまで遡れるらしい。ただ『千一夜物語』と名付けられているものの、そんなには存在せず、後世に書き足されたものも多いようだ。シンドバッドや魔法の絨毯やアラジンなど、私たちがこれこそが『アラビアンナイト』の世界だと思うものはこの類いとのこと。「ガラン版」をはじめ、日本でもく知られた「バートン版」や「マルドリュス版」などの書誌学、受容史と実に網羅されている。2022/11/12
へくとぱすかる
66
著者の出演したNHK「100分de名著」でおもしろさを教えてもらった。アラジンとかアリババの話は、子ども向けのリライトで知っているけれど、残念ながら全編を読んだことはない。文献としての歴史がくわしく解説され、時代とともに物語がつけ加えられてきた事情がよくわかる。そもそも「千一夜」というタイトルを、文字通りに解釈したのが発端なんだな。しかしもしそうでなければ、現在のような物語の宝庫にならなかったかもしれない。ラストで日本人の持つオリエンタリズムのねじれを指摘。無意識に植えつけられているイメージは怖いと反省。2023/04/22
Aya Murakami
39
ブロ友兼小説創作友達様おすすめの本。 アラビアンナイトという名前がさすようにアラビアのお話である以上に推理小説やルネッサンスの影響がある作品が西洋にとってのアラビアンナイトのようです。今の西洋における人間中心の世界観って結構中東の影響が大きいのかもしれない…。アルコールとかもアラビア語起源ですし…。2018/06/02
MUNEKAZ
17
アラビアンナイトを紹介した一冊。巻末に主要な話の要約があるので、「アラジン見ました」程度の認識でもなんとかついていける。広く中東に伝わってきた小話の集積がもとで、確かな原典があるわけではないこと。それが西欧で「発見」され、イスラム世界への複雑なまなざしも含みながら発展し、現在の所謂「アラビアンナイト」へと作り変えられてきた歴史がよくわかる。もはや物語ではなく「空飛ぶ絨毯」「魔法のランプ」といったパーツで理解されているというのは面白い。著者も言うように作品というよりは、新たに生成され続ける「現象」である。2022/08/27
柏もち
13
予想外の方向に詳しかった。現代のアラビアンナイト成立までの研究書といった感じ。誰の翻訳がいつ出てその翻訳者が何を考えていて文化にどんな影響を与えたのか、に興味がある人じゃないと本書の大部分がつまらないと思う。実際、物語の内容の方に興味がある私はつまらなかった。しかし後ろに載っている6ページに纏めた「本書に登場する主な物語」30個の要旨はあって良かった。2016/04/05