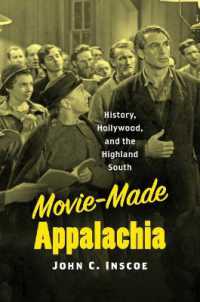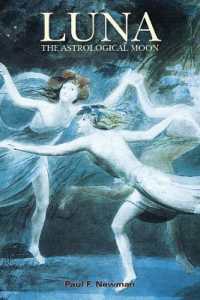内容説明
道徳的にみて「善い」「悪い」という判断には、客観的な根拠はあるのか。「赤い」「青い」などの知覚的判断や、「酸性」「アルカリ性」などの科学的判断とはどう違うのか。その基準となる「道徳原理」は、どのようにありうるか。ソクラテス以来の大問題を、最新の分析哲学の手法を用いて根底から論じ、倫理学の基本を解き明かす。
目次
第1章 道徳判断とは
第2章 「善し悪しは、その人しだい」とは?
第3章 道徳判断の客観性
第4章 行為・人柄の評価と実践
第5章 美徳と悪徳―呻きの沈殿と、共感
第6章 諸々の徳性と善悪
第7章 道徳原理
終わりに いい人生と、よく生きること
著者等紹介
大庭健[オオバタケシ]
1946年埼玉県生まれ。1978年東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。専修大学教授。専攻、倫理学、分析哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
大先生
7
難しい。分析哲学の手法を用いた倫理学の入門書。結論としては、善悪の見極めには普遍化可能性・不偏性をみたす道徳原理が必要(最大多数の最小苦悩という命題は道徳原理を定式化する際の基盤の一つになり得る)。善悪を見極めて悪を慎むことは、各自が人間としての「存在の承認」を危うくする事態へのセーフティー・ネットになる。「よく生きる」は必ずしも「善く生きる」によって実現できるわけではないものの、論理的に無関係とも言えない。とのことです。やっぱり難しい(苦笑)2024/10/01
teafool
3
「入門」というよりは「入門以前」「きっかけづくり」と言ったところか。その意味で、題名の「招待」という言葉のセンスが光る。最近この分野(哲学や倫理学)の本を少しずつ読んでいるものの、科学書や雑学本とくらべてまだまだ読みなれていないので、理解度は微妙なところ。1度読んで全体を把握した上で2回目を読むとよいかな?気になった部分もあるのだが、私の勘違いかもしれないので、後日もう一度読んでまた気になるようなら、そのときにコメントに書こう。要再読。2011/07/16
どらんかー
2
入門書であるらしいが、よくわからなかったが人は様々な考えがあるというのはわかった気がする。2018/06/24
やんま
2
入門書としては決しておすすめしない。 前半は主にニーチェや投影主義への批判で構成されている。その2つを予め知っておかなければ理解できない、という訳でもないが、面くらいはするだろう。 個人的には、意図してかせずかは知らないが、小賢しい構成だと感じた。初心者を対象とした本で、まず第一に「自分が勝つ試合を見せる」というのは、自分の論を強める手段として有効ではあろうが不愉快だ。 タイトルと袖の部分で惹かれて読むならば、後半(特に6、7章)だけで十分だろう。2018/02/20
空箱零士
2
「そもそも道徳は本当にあり得るの?」という問いかけから、「人‐間」同士の「気づかい」という関わりあいの観点で「善と悪」を論ずる内容? 徹して分析的に道徳・倫理を論じている筆致は非常に知的で刺激的。「お互いに」「気づかい」といった言葉はそれこそ普遍的ではあるが、分析的に書かれると改めて納得。「あとがき」で忠告されたものの、「呼応可能性」の重要性を改めて実感した。内容はそれこそ「招待」と言った感じで、(当然のことだが)答えは出ていない。私自身も理解しきれたとは言い難く、読み返して理解を深めたいところだ。2011/11/27
-

- 洋書
- HEDONIA