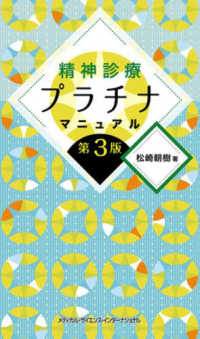内容説明
『記・紀』にみる神々の記述には仏教が影を落とし、中世には神仏習合から独特な神話が生まれる。近世におけるキリスト教との出会い、国家と個の葛藤する近代を経て、現代新宗教の出現に至るまでを、精神の“古層”が形成され、「発見」されるダイナミックな過程としてとらえ、世俗倫理、権力との関係をも視野に入れた、大胆な通史の試み。
目次
1 仏教の浸透と神々―古代(神々の世界;神と仏 ほか)
2 神仏論の展開―中世(鎌倉仏教の世界;神仏と中世の精神 ほか)
3 世俗と宗教―近世(キリシタンと権力者崇拝;世俗の中の宗教 ほか)
4 近代化と宗教―近代(国家神道と諸宗教;宗教と社会 ほか)
著者等紹介
末木文美士[スエキフミヒコ]
1949年山梨県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。東京大学教授。専攻は、仏教学・日本思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
52
西洋文明を理解するのにキリスト教を外せないし、資本主義を生んだのはプロテスタンティズムの職業倫理であると教えられるなど宗教史といえば西洋ものと私などは思い込んでいた。一方、日本の宗教といえば、寺社・仏像の美術的観点は身近だが、最終的に第二次大戦に突き進む国家神道に収斂する負のイメージしかない。あとは最澄・空海・親鸞らの伝記の断片。キリスト教により西洋史を語れるのと同様に、日本史を宗教によりどこまで語れるのか。本書は見事に語っている。仏教だけでなく神道や儒教にも力点を置き、現代までの宗教の通史として読みご↓2017/04/30
Book & Travel
31
史跡・寺社仏閣巡りをより楽しむための知識の補強と、わかり難い日本人の宗教観を歴史的に理解したいことから、継続的に宗教史の本を読んでいる。本書では古代の記紀神話から現代まで、日本の宗教と思想の流れが網羅的に書かれている。新書だけに著者も言っている通り極めて駆け足で、特に近代以降の国家神道、仏教、教派神道等の流れは複雑で本書だけでは理解しきれなかった。それでも、歴史を貫いてきた「古層」というものはなく、「古層」は歴史の中で作られてきたという観点は興味深く、得られた知識も多く、大いに勉強になった。2016/01/30
aponchan
28
司馬遼太郎氏の作品乱読している中で、日本の宗教、特に仏教や神道、キリスト教の位置づけなどを知りたいと思い、読了。正直なところ、前半部分は難しかったが、部分部分において理解できたので読んでよかった。戦後に関しては、身のまわりで目にする新興宗教団体の施設、オウムや9.11テロを含めた宗教と日本人の関係まで語られていたので、理解しやすく感じた。読んでみて感じるのは、やはり、司馬遼太郎氏の知見の幅広さ。これからも折を見て周辺知識を固めていく本を読んでみたいと思う。2020/05/06
さきん
25
いきなり、丸山氏の古層という概念を持ち込むことに違和感。神道がカミ信仰から変容しているのはもちろんのことだが、仏教の変容ぶりも大きい。オリジナルの仏教は、ブッタの哲学に留まるはずであったが、中国を経て、土着化してしまった。また、国家神道しかり、伊勢神道しかり、ある日本列島内の領域を統治するために各地の土着している信仰を束ねて整理したという政治的要素が大きいのではないかと思う。文献に資料が絞られている印象を受けたので、もっと考古学や民俗学の視点に触れてほしかった。2016/10/20
月をみるもの
24
なんで5世紀に日本にやってきて支配的になったのが儒教ではなく仏教で、江戸時代になると今度は武士階級で儒教が流行ったのだろう?(支配階級に有利な思想だから、、という理由だけなら5世紀に流行ってもよかったんじゃね?)という疑問が、本書を手にとるきっかけとなった。理由を一言で言ってしまうと、その時々の大陸側の流行りに習っただけでしょ、、、ってことでいいんかな。。葬式仏教と揶揄されて久しいが、人が一番宗教的になる(死を真剣に考える)のは、祭りでも結婚式でもなく葬式の時であることは確かな事実。2021/10/02