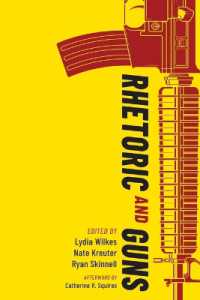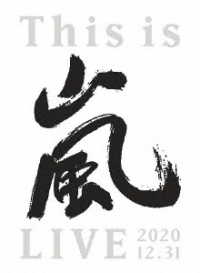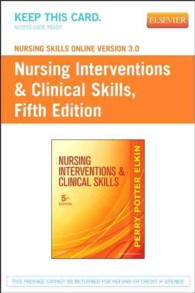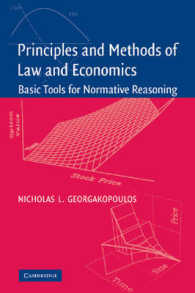出版社内容情報
発達心理学の立場から、幼児の「しつけ」「遊び」「表現」「ことば」の四つの相を取り上げて、その意味を明らかにする。子どもが自分を取り巻く世界に踏み出すための発達的基礎は、幼児期にこそ培われるべきことを提言。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Isamash
17
発達心理学を専門とする岡本夏木・元京都女子大教授の2005年出版の著書。幼児のしつけ、遊び、表現、ことばに関する著者の考えを述べ。しつけに関して、その中で子供が自己への信頼、誇り・自尊心の第一歩を踏み出すとする。遊びにより、倫理を実感し相手を読んだり人の心を読むことを育てる。そして表現活動により過程の楽しみや苦しみを実体験する。ことばに関しては、自分が相手に向けたことばが、その親しい相手を通して自分に投げ返され、それが自分自身の励ましになり人と人との根源的なところでの繋がりに結びつくと説く。成る程である。2022/01/03
魚京童!
16
私の脳みそがふやけていて理解ができなかった。最近ふやけている。もうどうにでもなれって感じ。生きることが続くことで、終わりがなくなった。魔の山に登ったまま。ただ生きている。昔はそうではなかったというか、区切りがあった。自分で作るしかなくなった。グライダー人間は楽だった。今年はあれ、来年はあれ、その次は。いまは大空で彷徨っている。どこでも行けるけど、別に行きたいところなんてない。今を生きるわけではない。未来にも過去にも生きていない。ただそこに在る。コロナだから余計そう思ってしまう。熱中してごまかすしかない。2020/08/30
1.3manen
14
中年の僕にもそんな時期があった。能力とは、社会に出た時、地位や収入につながるもの(10頁)。実際、非正規になってしまうと絶望的になるが。とりわけ、能力があって博士号あっても専業非常勤講師で雇用の危機に陥るということもままある。子どもも4歳になると理不尽を知り、5歳になると大人の身勝手さに批判的にもなるようだ(53頁)。時折、親が子を、子が親を、凶行に及ぶ親子も出てしまう昨今。大原敬子先生のような幼児教育のプロの社会的意義が問われるところである。収束しない放射能ダダ漏れの世の中に生れ落ちてかわいそうだが。2013/08/03
Nobu A
13
岡本夏木著書初読。深淵で重厚。論考を重ね、洗練された言葉で紡がれている。冒頭の問題提起で鷲掴みにされ、時折晦渋な表現を二度読みしながらも引き込まれた。高度化した経済活動やIT革命で幼児期の空洞化を懸念。キーワード「一次的ことば」と「二次的ことば」を対比させ、躾等を通しての子供との関わり合いや幼児期の「誠実な他者」の涵養の重要性を説く。「表現は、認知した世界を外在化させるだけでなく、表現することによって認知のしかたが変容してゆく」は目から鱗。幼児期からの発達移行を考えた情報教育学の体系化が必要。久々の良書。2022/03/08
ふろんた2.0
13
こんなに論理的にわが子考えながら子育てはできないけど、あっという間に過ぎ去る幼児期を大切にしようと思う。2015/09/30