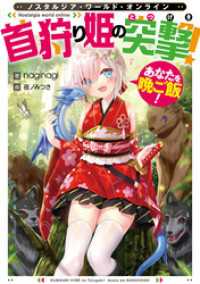内容説明
一面を同じ色で彩っては、一斉に散っていくソメイヨシノ。近代の幕開けとともに日本の春を塗り替えていったこの人工的な桜は、どんな語りを生み出し、いかなる歴史を人々に読み込ませてきたのだろうか。現実の桜と語られた桜の間の往還関係を追いながら、そこからうかび上がってくる「日本」の姿、「自然」の形に迫る。
目次
1ソメイヨシノ革命(「桜の春」今昔;想像の桜/現実のサクラ)
2 起源への旅(九段と染井;ソメイヨシノの森へ;桜の帝国;逆転する時間)
3 創られる桜・創られる「日本」(拡散する記号;自然と人工の環)
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





稲岡慶郎の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
77
社会情報化論の本で知った社会学者が桜の本を出しているときき、手に取る。現在代表的な桜の品種とされるソメイヨシノの歴史的な実像、近代化以前の一般的な桜の種類や、明治ごろからのソメイヨシノの普及と世間的な言説などを多数の文献を参照しながら考察。ナショナリズムと結びつく日本の象徴としての花と言説の相互作用を語る。なかなかスリリングな考察なのだが、やや読み飛ばし気味だったのは桜にそこまで興味がわかなかったせいか。ちょっと反省。2018/12/16
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
42
ソメイヨシノは全てクローン(=接木もしくは挿木で繁殖した、全て同じ遺伝子個体の品種)であることは元々知っていた。 しかし、「桜といえばソメイヨシノ」なイメージの真実と、それがどのように「日本」のイメージとして定着していったか、についてはとても興味深かった。2020/06/11
1.3manen
24
巻頭にカラー2頁分。 昨日の箕輪町の桜(大出城跡)はよかった。 その先でスピード取り締まりしてたけど。 18頁の桜前線の地図によると、 ぼくのところも20日前には 咲く感じだ。 吉野の桜のように、特定の桜に結び付けたがるのは、 近代人の悪い癖(44頁)。 和歌の世界でも吉野を見ずに吉野が詠われた(55頁)。 ソメイヨシノのソメイは、 東京染井とは知らなかった(56頁~)。 ナショナリティを体現する桜(92頁)。 大正期の飯田(119頁~)。 長野県はエドヒガンの多い地域(121頁)。 2014/04/13
ochatomo
13
著者の専門は比較社会学・日本社会論 サクラは自家不和合性で種子から育てると別物 ソメイヨシノはオオシマザクラとエドヒガンの交配で、染井は園芸地、吉野は吉野桜の一種をあらわす 山桜の赤い葉より更に「桜らしく」明治の新しい時代に新しい桜として植栽広まる 2005刊2015/02/23
りょう
12
春の息吹が感じられる今日この頃。そろそろお花見シーズン。お花見といったらやっぱり桜、桜は「日本らしさ」の象徴だよねぇ。そう、昔から愛でられてきた、あの一面に咲き乱れる桜・・・。え?そういう光景はここ100年くらい前の出来事だって?いやいやそんな最近なわけないでしょう。桜はずっと昔から愛されてきてるでしょ。桜は昔の有名な人たちが桜のことを歌ってたじゃん?え。あれは想像上の産物だけれども、ソメイヨシノの出現で虚構が現実になった?何言ってんのかよくわからない・・・2014/03/24