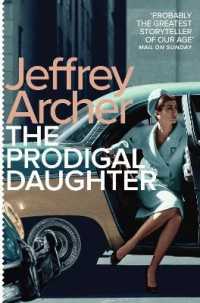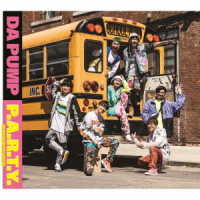出版社内容情報
英単語をいくら知っていても,英語が使えるようにはならない.一語ずつ「訳す」発想から「いかに意味を伝えるか」に意識を切り替えれば,簡単な言葉で生きた英語表現ができるようになる.そのための方法を具体的に伝授する.
内容説明
「国際情勢」はInternational situationと、すぐ思い浮ぶだろうが、実際はwhat’s going on in the worldといった方が、より具体的で意味がわかりやすい。日本人が陥りがちな、一語ずつ「訳そう」とする発想から「いかに意味を伝えるか」に意識を切り換えれば、簡単な言葉で生きた英語表現ができるようになる。そのための方法を具体的に伝授する。
目次
第1章 英語と日本語の違い
第2章 日本語は名詞、英語は動詞―日本語の名詞から英語を考える
第3章 日本語は抽象的、英語は具体的―日本語の文(センテンス)から英語を考える
第4章 「一事一文」の原則―日本語の文章から英語を考える
第5章 英語の構造と日本語
終章 体験的英語教育―私の提言
著者等紹介
長部三郎[オサベサブロウ]
1934年新潟県長岡市生まれ。1959年東京大学教養学科(国際関係論)卒業、アメリカ国務省言語部勤務(日本語通訳担当)、(社)日本ペンクラブ事務局長などを経て、現在、桐蔭横浜大学工学部教授、桐蔭国際交流センター長、サイマル・アカデミー講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価