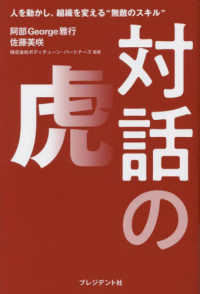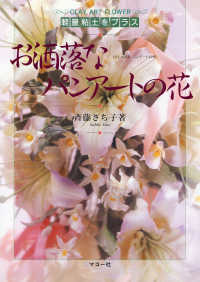出版社内容情報
“超高齢社会”へ向かいつつある日本.誰でもが豊かな老いを迎えられる処方箋はあるのだろうか.長年にわたって医者として高齢者の地域医療に携わり,訪問看護や24時間ケアを先駆的に実践し,さらに行政にも提言している著者が,いまの医療と福祉の問題点をみずからの体験を基に指摘する公的介護保険など,これからの医療・福祉の可能性を語る.
内容説明
超高齢社会へ向かいつつある日本。誰でもが豊かな老いを迎えられる処方箋はあるのだろうか。長年高齢者の地域医療に携わり、訪問看護を先駆的に導入し、さらに行政にも提言している著者が、介護などいまの問題点をみずからの体験をもとに指摘しながら、ターミナルケア、公的介護保険など、これからの医療・福祉のありかたを熱く語る。
目次
1 高齢者介護問題と日本の家族
2 高齢化急進展の意味するもの
3 高齢者医療と福祉の軌跡
4 高齢者介護の実践
5 新ゴールドプランから公的介護保険へ
6 高齢者の医療―とくにターミナルケアについて
7 日本の福祉は、なぜよくならなかったのか
著者等紹介
岡本祐三[オカモトユウゾウ]
1943年大阪に生まれる。1968年大阪大学医学部卒業。阪南中央病院内科医長・健康管理部長を経て、現在、神戸市看護大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
21
この本を読むと、発刊当時(1996年初版)からあまり自分のお年寄りに対する意識は変わっていないのでは・・・と思ってしまった。大切なのは「寝かせきり」にしないこと。看ている側としては難しい問題だと思うが、いかにそのかたの尊厳を保ちつつ、ケアをしてさしあげるかということに尽きる。数十年後はわが身と思えば変わってくるはず。2013/10/06
ヒナコ
5
介護保険制度の開始が立法化される1997年の一年前に、高齢者医療を担う医師によって書かれた新書。95年の「新ゴールドプラン」の策定から2000年に始動する介護保険制度の間の激動期の息づかいを感じることができた。→2021/03/13
なめこ
4
介護離職ゼロが謳われる昨今、日本の介護の歴史を辿れる1冊。「昔は家族が年寄りを看たものだ」という“古き良き日本像”は誤解である、ということが統計と証言で示される。つまりは養老院=困窮者の世話、という政策により「役所の世話になるのは恥」という観念が染みついてしまったことの、単なる裏返しなのだ。「親孝行したい時には親はなし」という平均寿命50歳のころの言い回しは70、80、さらには…、という時代には多少無理がある。もちろん親の有り難みと、命がいつなんどきどうなるかという意味では普遍的なんだけど。1996年刊行2016/01/16
脳疣沼
2
良書。出版時は1996年であるから、もう20年も前のことだが、そうだからこそ介護保険制度が生まれるまでの切迫した社会状況がよく分かる。若い人(私だ)は、当時の社会通念を知らないものである。昔は家庭内で介護を上手くこなせないことを「家の恥」としていたというのは驚きだった。また、特別養護老人ホームの「特別」の意味も初めて知った。老人医療無料化政策の思わぬ副作用も、そもそもの認識の甘さも、その後の認識の転換も、全て考えさせられる。当時に比べたら確実に改善している。結局、政府も長い目でみたら国民の声には抗えない。2017/03/14
いも けんぴ
1
介護保険制度ができるまでの高齢者福祉行政のあらましが理解できた。この15年でもまったく状況が変わっているし、以前にはなかった問題が噴出してきている。今後も状況の変化にあわせて、介護行政が大きく動いていくのだろうと思った。2012/10/27