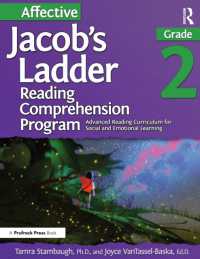出版社内容情報
日露戦争直後,東京市の警察署の八割が襲撃される日比谷焼打事件がおきた.だがわずか十数年後,関東大震災では「自警団」が登場し,民衆はすすんで「治安」に協力する.この変化は何を意味するのか.「民衆の警察化」が典型的に押し進められた大正デモクラシー時期を中心に,社会生活のすみずみにまで及んだ「行政警察」全体像を解明する.
内容説明
日露戦争直後、東京市の警察署の八割が襲撃される日比谷焼打事件がおきた。だがわずか十数年後、関東大震災では「自警団」が登場し、民衆はすすんで「治安」に協力する。この変化は何を意味するのか。「民衆の警察化」が典型的に押し進められた大正デモクラシー時期を中心に、社会生活のすみずみにまで及んだ「行政警察」の全体像を解明する。
目次
序章 警察廃止をめぐる2つの事件
1 行政警察の論理と領域
2 変動する警察
3 「警察の民衆化」と「民衆の警察化」
4 「国民警察」のゆくえ
終章 戦後警察への軌跡
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
無識者
15
警察は嫌われる存在から、治安維持を遂行する正義の担い手へと変貌する。自警団が数多くつくられるようになり、それが警察の手足となり治安維持活動をする。警察の業務を自警団に分担させることにより、過失が起きた際には責任逃れに使われた。一億総監視社会である。その中で起きた悲劇が関東大震災の時に行われた朝鮮人の取り締まりである。現代とのつながりはあまり見えなかったので機会があったら授業に潜り込んで聞いてみようかなと思う。2016/07/15
壱萬参仟縁
13
緊急性もないのに110番する時代。これでは、緊急の意味が問われても仕方ない。大事にするのが好きな輩すらいる。民衆は一面で警察を恐怖し、非難しつつ、他面で警察から離反し、警察を忌避していった(7頁)。そんな時代もあったのだ。1926年の長野県警廃事件(15頁~)。通訳案内士の話も出てくるが、当時は3次試験まであったし、今は国交省だが、昔は案内業は警視庁が実施していたとは(48頁)。2013/08/02
kenitirokikuti
9
図書館にて。映画『福田村事件』の後、関東大震災後の朝鮮人虐殺って線でいろいろ読んで、この警察史ものを手にしたのだった。藩閥が民権派を抑えるため警察機構を積んでいく、というのが叙述の筋。この著者は早稲田の出身なので、反・立憲政友会という立場なんだろう、と理解した▲もう令和5年にもなると、冷戦下の昭和後半でさえ歴史になりつつあるので、戦前には「地方自治体の地方公務員」ってのはナイぞ、ってなことを思い出す必要があった。2023/10/10
ヨミナガラ
9
“一九二〇年代の前半、社会運動の高揚に対抗すべく、「力の警察」が強調されはじめ(中略)治安維持法の制定(中略)特高警察の大拡張をへて、国民の政治的・社会的な諸権利を圧殺する体制が成立する。以後、ファッショ的な気運の昂進と、戦時体制の深まりの中で、警察はその権限を極限にまで膨張させ、(中略)「警察国家」が閉塞した社会を覆い、権力の末端組織に編成された国民は「国民皆警察」化して、相互監視と異端摘発をこととしながら、地域を「自衛自警」していく。結局、警察は「民衆化」されず、民衆は「警察化」されたのである。”2014/05/11
Mealla0v0
5
本書は、日清・日露戦争~大正デモクラシー=国民国家意識の形成期に焦点を当て、近代日本における民衆の警察経験を論究する。戦前の警察を特徴づける「予防」の視点は、社会のあらゆる領域に介入し、民衆を道徳化する機能を負う。これを行政警察と呼ぶが、この形成過程は、これは単に暴力装置として力を背景とした抑圧から、民衆を保護する存在への変化だったと言える。それは警察の民衆化であると同時に、自治組織の形成促進など、国民を警察行政の一環に捉え込む民衆の警察化でもあった。その意味で、特高は特異例でなく到達点だったと言える。2021/01/03